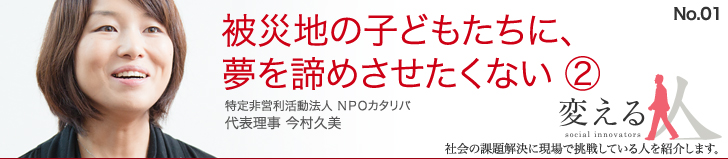子どもたちの未来に、たくさんの選択肢を

大槌復興への力強い決意が描かれた幕
今村久美さんのインタビュー第1回はこちら:「家や学校を失った子どもたちに勉強の場を」
世界に目を向け、自分の町を愛せる人に
コラボ・スクール「大槌臨学舎」が開学したのは2011年12月。目前に迫った高校受験に備えるため、中学3年生の受験勉強をサポートすることに全力が注がれた。子どもたちとコラボ・スクール、お互いの努力の甲斐あってほとんどの生徒が志望校に合格。彼らを無事に送り出し、コラボ・スクールは4月から新しい中学生を迎えるはずだった。だが、彼らの姿と、その変化を感じて、今村さんはある決意をする。
「支援活動に取り組む中で感じていたのは、いちばんの敵は無関心だということ。普段は無関心でいるのに、例えば行政がなにかを決めると、反対側からしかものを言わない。それじゃなんにも変わらないし、変えられない。でも、あの厳しい状況の中で受験に立ち向かった子どもたちを見ると、“学びの機会をもらった分、自分たちが町のために何かしなきゃ”、って強い思いが感じられました。『町のためになにかしたい』とか、『将来大学を出て、そしたら絶対戻ってきて、お父さんの会社を継いで復興させるんだ』って、まだ中学生の子たちが言うんです。そんな様子を見て、彼らが高校生の間に、まちづくりに具体的にコミットする機会をつくらなくては、と思いました」
子どもたち自らが、主体的に将来を考え、実現に向けて挑戦することによって、周りを動かし、ものごとを変えていけるという実感を持ってもらいたい。こうして、高校生が取り組む「マイ・プロジェクト」がスタートした。
「大槌町の子どもたちは、町を思う気持ちがとっても強いんです。地域社会や祭り文化の中で、郷土愛を育むしくみが残っているんでしょうね。とは言っても、いまの大槌町を取り巻く環境は本当に厳しくて、残ったものに依存するだけでは立ち行かない時がきっと来るはず。だからこそ、自分の頭で考えて、チャレンジして、新しいことにどんどん取り組める大人になっていって欲しい」
マイ・プロジェクトには、コラボ・スクール1期生の高校生10名が参加している。町の高齢者を元気にしたいとイベントを企画する子、津波で写真が流されてしまった家庭に写真を撮ってプレゼントする子、「被災地」ではなく「星のきれいな大槌町」と呼ばれたいと星ガイドを務める子。それぞれが、自分の生活圏でできるチャレンジを、自分自身で見つけ、取り組んできた。
「地縁血縁は大切にしてほしい。でも、その中に閉じこもりきりになってはほしくない。できたら、世界と広く繋がりながら、自分の育った町を愛せる人になってほしい。まさに、“Think globally, act locally”ですね。それを子どもたちが体験できる機会をどうやってつくっていくか。私たちにとっても毎日が挑戦です」

大槌臨学舎でマイ・プロジェクトに取り組む吉田くん
忘れられた石碑の教訓
第1回に登場した吉田くんもまた、マイ・プロジェクトに取り組むひとりだ。彼は、明治三陸津波の被害を伝える石碑を、震災の後になって知った。そこには当時の死者数が、さらには「ここに家を建ててはいけない」「ここより下は、津波が来たら高台に逃げろ」という警告が書き記されていた。後悔の念が募ったと彼は言う。
「この石碑を読んでいれば、読んで多くの人に広めてみんなが防災意識を共有していれば、もっと多くの人が助かったんじゃないかって。僕は、震災を生き延びた大槌の人間として、後世になにか伝えたい。それは明治三陸津波のときに石碑を建てた人たちの思いと、きっと同じだと思うんです」
彼が着目したのは、なぜか「木」碑。丈夫そうな石ではなく、木こそ望ましいと語る彼の論理は明快だ。
「石碑だと、そのうち風景の一部になって、誰も気に留めなくなってしまう。それが、忘れ去られてしまった石碑の教訓。だから、木がいいと思いました。木だったらどうしても腐るし、字もかすれていくから、手入れが必要だし、何年かごとに交換もしなければいけない。そのときに震災の記憶を振り返ることで、この津波の教訓を後世に繋いでいけると思ました」

吉田くんが立てた木碑。「大きな地震が来たら戻らず高台へ」と刻まれている
震災の経験を、いちばん生かせるところにいたい
そう語る吉田くんも、マイ・プロジェクトの開始当初は、なにをしていいかわからなかったという。彼の心を動かしたのは、2012年の年末に宮城県で行われた「全国防災ミーティング」。被災地内外から中高生が集まって防災について語り合う中で、彼のやる気に火がついた。
「最後に参加者全員で集まって、被災地の建物を原爆ドームのように保存するかしないか、二組に分かれて討論会をやったんです。僕は、残すのは費用もかかるし、だったらその分をこれからの防災のために使ったほうがいいと思って、反対派にまわりました。だけど、賛成派もなかなか譲らなくて、時間切れになってしまいました。あそこで、スイッチが完全に入りました。遺構として残す以外にも方法があるはずだって、もう、自分じゃないみたいでした」
設置場所を確保するのは容易ではなく、加えて部活の最中には骨折と、その後も苦労は重なった。だが、コラボ・スクールのスタッフ、安渡古学校区の住民、クラスメイト。多くの方々の協力を得て、ついに今年3月11日に木碑を建てることができた。彼のマイ・プロジェクトは、ここで終わらない。夢は、大学に進学して防災を専門に学び、消防士になることだ。
「大槌に帰って来ようと思ってはいるんです。でも近い将来、東京で震災が起きるって言われているじゃないですか。もしほんとうにそうなったら、震災経験者である自分たちが役に立てるかもしれない。生きることの重みを知ったからこそ、一人でも多くの人たちを救いたい。そう思うと、自分の力がいちばん生かせるところなら、大槌でも、東京でもいいのかな、って思います。どっちにしても、常に最前線にいたいですね」
東海・東南海・南海地震が起きた場合に、津波による甚大な被害が予想されている静岡県などで、自分たちの経験したことを伝えたい、という思いもある。学校の勉強に、部活に、マイ・プロジェクトに、と大忙しの吉田くんだが、全力で立ち向かっているうちに、志望大学や行政との縁もつながりはじめている。
「やばいかもしれない。ほんと、戻れないところまで来ちゃったかもしれない。いろんなところで話すと、話した分だけ、縁も責任も広がっていくから」
吉田くんのまなざしは、復興のその先に向けられている。その姿は、まさに、“Think globally, act locally”だ。

NPOカタリバ 代表理事 今村久美
つまらない日常を変えるのは自分自身
コラボ・スクールにめぐり会えたことで、吉田くんの世界観は大きく動き始めた。それは、今村さんがNPOカタリバを立ち上げた思いに重なるところがある。岐阜県高山市に生まれ育ち、故郷を離れて進学した慶應義塾大学環境情報学部。彼女のキャンパスでの日々は、驚きと刺激にあふれていた。
「留学経験のある人がとても多かった。私の故郷で帰国子女なんていったら、ちょっとした有名人。駐車場にはBMWとかベンツとか、外車もたくさん停まっていたりして。いままで自分が生きてきた生活圏とは、ちょっと違う世界に来てしまったと、素直に思いました。でも、良い先生や先輩、友人にめぐり会えて、いろんなことにチャレンジさせてもらって、本当に楽しい大学生活でした」
だが、一歩大学を離れると、「大学がつまらない」「早く卒業して働きたい」という友人が少なくなかった。誰かがこの日常を何とかしてくれないか、そんな雰囲気に以前の自分を感じたという。
「私も、先生への不満とか親への不満とか、高校生までは当たり前のように持っていました。高山を出たかったのも、“出る杭は打たれる”ような環境がつまらなく思えて。私が悪いんじゃない、この場所が悪いんだって、どこかで思っていたのでしょうね」
大学で出会った、意識が高く意欲的な人たち。彼らとの間にある温度差は何なのだろうと思うほどに、違和感を覚えた。日本中を見渡したら、決してお金があって教育環境に恵まれる人ばかりではない。「なんか不条理だ」。そう思ったところに、気づきが生まれる。
「日常を自分で変えるなんて、そんな選択肢すら知らないまま、大人になっていく人が多いと思うんです。だけど、私は大学でチャレンジすることの大切さを知りました。そういうチャンスがあることのありがたさも。だから、“実は、日常を変えるのは自分自身なんだ”ということを実感できる機会をつくっていきたい、と考えるようになりました」
生まれ育った環境のせいで、選択肢にこんなに差が生まれるなんておかしい。でも、もしかすると「日常ってつまらない」という感覚も知っていることが、むしろ強みになるかもしれない。地方に住んでいることの不便さや苦労も、だからこその経験を武器にする、ピンチをチャンスに変えていける、そんな人材を生み出す機会になるかもしれない。そんな思いがカタリバを立ち上げるきっかけとなったという。
「対話を通じて、“こんな大人になれるんだ”“こんなチャレンジ自分もしてみたい”と思えるような、将来のことを主体的に考える機会を学校教育の中につくりたかった。自分の中にあったコンプレックスをバネに、自分自身が感じてきたことをどうしても授業に置き置き換えていきたかった。その思いが、いまにつながっています。カタリバにも、コラボ・スクールにも」
コラボ・スクールに通う子どもたちに、今村さんは希望を感じているという。厳しい環境におかれているからこその気づき、挑戦、そしてたゆまぬ努力。彼女が女川町や大槌町に足を運んだのは、運命だったのかもしれない。

コラボ・スクール授業風景。講師には大学生ボランティアも多い
コラボ・スクールから繋がる、広がる出会い
コラボ・スクールは子どもたちだけではなく、カタリバにも新しい機会をもたらしている。大槌臨学舎のスタッフである川井さんは、震災後に勤めていた会社を辞め、まったく畑違いの世界に飛び込んだひとりだ。
「震災前はシステムエンジニアをしていたんです。でも私は宮城県の出身で、被災地も、復興の状況も、まったく人ごととは思えませんでした。未来をつくっていく子どもたちのために、自分にできることは何かないかと思い続けて。そこでコラボ・スクールを知って、思い切って飛び込んだんです」
大槌町は、川井さんの生まれ育った地域ではなく、以前からよく知っていたというわけでもない。だが、地域の子どもたちや保護者の意識が、少しずつ、でも確実に変わってきていることを実感しているという。
「この辺りは、もともと大学が近くにない。だから、大学生もいない。日常的な存在ではなかったんです。そこに、大卒のスタッフたちが入っていって、大学の話をする。ボランティアでやってくる大学生という人種に出会う。コラボ・スクールに来るまで違う仕事をしていたスタッフに触れる。そうした中で、大学という存在が身近なものになってきました。これまで縁遠かった生き方を見て、自分たち自身のこととして考えるいい機会になっていると感じます」
当初は無料だったコラボ・スクールも、今年からは月額5,000円の学費を設定している。支払いが難しい家庭向けには奨学金枠も設けてある。有料になると通ってくる子どもが減るのではないか、という声もあったが、その数は一年目とほとんど変わってはいない。このことに、今村さんは可能性を感じている。
「震災後の厳しい中にあっても、子どもにやる気があるのならコラボ・スクールに行かせてあげたい、という親御さんの意志の表れだと受けとめています。むしろ有料にすることで、私たちが試されている部分もあると思うし、やっぱり責任も大きい。その意味でも、無料の時にはあまりなかった、お互いの価値を確認し合って、よりよいものにしていこうというようなコミュニケーションの機会が増えたことは良かったと思います。子どもたちにとっても、私たちにとっても」
立ち上げ時には、「ここにそんなものをつくっても誰も来ない」とまで言われたコラボ・スクール。それが今では、「1年間通わせてみて、やっぱりこれからも行かせたいと思った」「子どもにとっても、東京から来た若い人たちとの出会いが刺激的でいい」といった声が数多く寄せられる、かけがえのない存在となっている。今村さんやスタッフの熱意が、子どもたちの未来を、そして地域そのものを動かしつつある。(第3回「私たちと地域の未来に、新しい可能性を」に続く)
【今村久美 略歴】 いまむら くみ*1979年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。大学在学中に2001年に任意団体NPOカタリバを設立し、高校生のためのキャリア学習プログラム「カタリ場」を開始。2006年には法人格を取得し、全国約400の高校、約90,000人の高校生に「カタリ場」を提供してきた。2011年度は東日本大震災を受け、被災地域の放課後学校「コラボ・スクール」を発案。
【取材・構成:熊谷 哲(PHP総研)】
【写真:shu tokonami】