デジタル社会における憲法のあり方を考える(後編)

新型コロナウイルスの感染拡大、新しい国際秩序に向けた世界の動き、デジタル化、人権問題等、さまざまな問題を背景にして2022年4月に、PHP「憲法」研究会が発表した提言報告書『憲法論3.0 令和の時代のこの国のかたち』(以下、『憲法論3.0』)
憲法は、改正の是非の議論を克服し、社会の変化にいかに応えるべきか、具体的な論点は何か、社会や政治はどのように動いていくべきか、『憲法論3.0』掲載の論考に込めた思いや考えについて、2回に分けて執筆陣が会し、議論しました。
本稿は、第2回目前編に続く座談会の後編。宍戸氏、山本氏に、「これからの憲法を巡る動きはどうなっていくか」「読者にも考えて欲しいところ」「読者へのメッセージ」を語っていただきました。
1.これからの憲法を巡る動きはどうなっていくか?
■言論空間の健全化とプラットフォームの規律が課題
亀井 宍戸さんが仰ったように、多様な人たちが共生していく社会の形成は喫緊の課題です。だからこそ、デジタルとセットにやっていくというイシュー・セッティングが必要なのではないでしょうか。こうしたイシュー・セッティングの推進は「デジタル現存在」への配慮、ひいては包摂性の実現や「システム2」の機能発揮にも繋がっていくと思いますが、留意すべきポイントはどのようなところにあるのでしょうか。
宍戸 デジタルとセットにしたイシュー・セッティングでは、詰まるところ、プラットフォーム事業者にとってのインセンティブがどこにあるのかという話になるでしょう。プラットフォーム事業者からすれば、「システム1」に流れるようなアーキテクチャーを自分たちは作りたくて作っているわけではなく、それが儲かるからやってしまっただけだ、ということでしょう。
政治家もインセンティブの問題が大きいと思います。政治家は小選挙区制度のなかで生き残っていかねばなりません。そのなかで政治活動をやろうとしたら、やはり、個々の議員としても党としても、「システム1」に訴える行動をするのが「合理的」ということになります。ただし、そうでない政党も確かに存在します。「システム2」に依ることで、自分達の支持基盤を固め続けられる政党があるかもしれません。
野党側が多数を取ろうとするなら、「システム2」で頑張って議論して、今の政権与党を支持するはずもない有権者の票を取りに行くという戦い方もあるはずですが、安易に「システム1」に手を出して、目の前の非自民の政党票を取り合い、逆に分裂してしまっている印象もあります。
山本さんの論考に話を戻します。「憲法論3.0」では人権部分、つまり、市民的な自由と平等の話については、デジタル社会のバージョンアップに寄っています。その分、地域全体を動かすエコシステムとか、経済的インセンティブへの論究がないことへの批判もあると考えられますが、山本さんはこうした課題をインフォメーション・ヘルスの議論で回収されようとしたり、全体像を描かれたりしているものと受け止めました。ですから、「憲法論3.0」の議論は山本理論の一部だということが、1つ抑えるべき点ですね。
もう1つ、プラットフォーム規制について、この議論をしっかりやろうとすれば、我々公法学が持ち合わせている伝統的な武器は「公企業」論だということです。
亀井 企業は社会の公器という話にも繋がりますね。
宍戸 そうです。もちろん、公企業をどうするかという、かなり強い監督の仕組みだけで全ては上手くいきません。
公企業が経済的に不合理だからということで、新自由主義の理屈が通って、通信自由化をやったことが、その証左です。通信自由化をしなかったら、世界に冠たるiモードとEmoji文化は生まれず、SNSを受け入れる余地もなかったのではないでしょうか。ただ単に海外のプラットフォームに乗っかって完全に占領されたか、逆にただのデジタル鎖国か、どちらかだったのではないでしょうか。
問題はここからどうするかです。1つめは、海外プラットフォーム事業者に対して実体規律を課すことはかなり難しいので、手続規律を課していく方向です。総務省「プラットフォームサービスに関する研究会」(以下、プラットフォーム研)の検討内容で言うと、偽情報対策については、モニタリングを法的に義務付けるけれども、具体的に何をしろ、これをしろとは言わない。長期には対話路線で行くしかないでしょう。日本社会特有の問題としては、部落差別が一番焦点になるでしょうが、そこは鬩ぎ合いでしょう。
残る公企業論の筋は、海外プラットフォーム企業と抑制均衡しうる公企業的な事業体を日本国内で創ったり維持したりすることでしょう。1つは、既存のインフラ産業です。具体的には、ドコモ、KDDI、ソフトバンク等について適正な規律を掛けつつ、均衡できるような状況を生み出すことです。これを言い出すと当然に、放送制度、NHKの問題が出てくるはずですが、この辺を山本さんはどうお考えですか?
山本 宍戸さんが仰るように、インセンティブ設計の問題は重要です。インセンティブ設計を統治構造のなかに組み込むという発想は、『フェデラリスト・ペーパーズ』を持ち出すまでもなく、憲法にもともとビルトインされていたもので、憲法論そのものだと思います。現代的に必要なのは、そこにデジタルやテクノロジーをどう絡ませるか、またプラットフォーム権力をどうその仕組みのなかに位置づけるかでしょう。
プラットフォームに関して言えば、まず、「透明性」なのかなと思います。現在のプラットフォームのアルゴリズム1 は、ほぼ完全に商業的なものになっています。儲かるためにレコメンデーションをかける。そこに心理学だとか認知科学の知見が多く活用されているわけです。なかにはエンゲージメントを得るために、ユーザーをわざと中毒状態に陥らせるものもある。今後は、レコメンデーションのロジック等を透明化することで、そのような悪質なプラットフォーム事業者を市場において断罪することが重要です。マインド・ハッキングのような手法でユーザーのアテンションを不当に奪う企業は儲からない、逆に、ユーザーのインフォメーション・ヘルスに配慮するような企業は儲かるといった市場を作出することが重要です。もちろん、市場が少数のプラットフォーム事業者に寡占されていれば、透明性を確保して悪質なアルゴリズムが明らかにされても、結局ユーザーに選択の余地はないことになりますので、競争法的な規律を同時に模索することも重要でしょう。
また、宍戸さんがご指摘された2点目と関連しますが、新聞や放送のような既存メディアを、アテンション・エコノミーの行き過ぎを監視する存在として、言い換えればプラットフォーム事業者による「権力」濫用を監視する存在としてサステイナブルなものにしていくことが重要だと思います。ヨーロッパやオーストラリアでは、既存メディアのニュースをプラットフォームが使用した場合の対価について、プラットフォーム側に誠実に交渉に応じる義務を課す国も出てきています。ここでは国家が、プラットフォーム企業と既存メディアとの力の格差を埋める積極的な役割を果たしています。
ただ私は、国家が、海外のものを含めプラットフォームをガチガチに規制することには否定的です。フランスやドイツでは「デジタル主権」(digital sovereignty)の考えがとられ、国家がプラットフォームからデジタル領域における主権を奪還しようという動きが強くなっています。近代主権国家体制を踏まえれば、まことに理解できる動きなのですが、国家が主権的権力を本当に独占すべきかについては、慎重な見方が必要だと思います。たとえば、トランプのような不動産王が大統領になって、プラットフォームに対して相当介入するような場合には、プラットフォームが国家に対抗してリベラル・デモクラシーを擁護する役割を果たすことがありえます。実際、2021年1月の連邦議会襲撃事件では、大統領主導の「国家的クーデター」からリベラル・デモクラシーを守ったのは、TwitterやFacebookのようなプラットフォーム事業者だったとも言えます。もし仮に、国家が厳格な規制でプラットフォーム事業者を雁字搦めにし、手懐けていたならば、プラットフォーム事業者は大統領や大統領支持派のアカウントを停止するといった強硬措置はとれなかった可能性があります。通信品位法230条がプラットフォームの自律性を広範に保障していたことが、リベラル・デモクラシーを守るための、プラットフォーム事業者による対国家的措置を可能にしたという側面もあるように思います。
亀井 一方、プラットフォームが国境を越えて市場を寡占化していく可能性があります。そうすると、経営的に持続できないメディアが生じるかもしれません。その時に、「NHKをどうしていくのか」、あるいは、山本さんが指摘された「新聞をどうしていくか」という話にもなると思います。
そこで敢えて「日の丸メディア」と言いますが、国家として日の丸メディアを持っておくため、場合によっては、公的資金を入れなければならない場面もあるような気がしますが、ここはどう思われますか?
山本 公的資金の前に、先ほど申し上げた誠実交渉義務のような競争法的な介入も考えられます。また、放送については、放送に対するユーザーのアクセシビリティを確保するための制度等も検討されて良いでしょう。今、テレビを見る人はかなり少なくなっています。ドン・キホーテ等ではチューナーレステレビがバカ売れしているわけですね。放送がその公共的な役割を果たしている限りで、それへのアクセシビリティを高めていくような仕組みを設けて良いように思います。ゲートキーパーと化しているプラットフォームのトップページの目立つところに放送コンテンツを置くとか、バス停のデジタルサイネージ等で放送を優先的に流すといった方向性ですね。これまで新聞や放送は、私たちの日常的なルーティンと深く結びついていました。アクセシビリティを高めることで、そういうルーティンとメディアとを再接続させることが必要だと思います。ただ、それにはメディア側の自己改革も不可避でしょう。
宍戸 いわゆる「日の丸メディア」は、やはり必要なのではないでしょうか。イギリスに世界に冠たるBBCがあり、アメリカに3大ネットワークがあるように、アジアで何が起きているのか、アジアのなかでの日本の立ち位置、日本社会が何を考えているのかを発信することは、国際的な相互理解を促進し、日本の安全と繁栄のためにも必要でしょう。これはNHKワールドを始める時の議論の出発点でもあったはずです。ところが、メディアとして財源が持たない、人材も含めて全体としてサステイナブルでないということが、非常に大きな問題となってきました。
短期的に言うと、日本社会はそれなりの市場規模があったとはいえ、放送局を作り過ぎ、多元的に過ぎるという問題を抱えていると思います。ある種の市場原理を入れてしっかりした経営基盤を持ち、デジタル社会において、きちんとジャーナリズムを担えるようなメディアに再編していくことは焦眉の急ではないかと思います。
一方で、それでもサステイナブルではないかもしれない、という問題は残ります。仮に国のお金を入れる時には、先ほどのプラットフォーム規制の話にも関わりますが、実体規律をしないで手続規律はします、お金のパフォーマンスは見るけれども、中身のパフォーマンスは見ないし、「システム1」の方に寄っていくような要請もしないことが必要です。
NHKは、国民のなかに意見を言いたい人がたくさんいるので、そうした声を的確に公共放送事業に反映するためには、独立行政委員会等のいろいろな仕掛けが必要です。そうした仕掛けなしで公共放送をやろうとするなら、ダイレクトに税金を入れるというよりも、新しい公企業特権を与えるのが良いのではないでしょうか。
たとえば、視聴データの利活用です。一般のプラットフォーム企業がやるようなターゲティング広告等をやらないことを前提に、公共放送としての役割を果たすために必要な視聴データの収集、および、特権的な利活用を一定のガバナンスの下で行えるよう制度整備を行うことも考えられます。
亀井 大切なことは「何が公企業なのか?」ということなのでしょう。
宍戸 そうです。そこなのです。
山本 今の文脈では、アテンション・エコノミーから距離をとって健全な言論空間を支える存在、インフォメーション・ヘルスにコミットし、私たちの「システム2」を守る存在ということでしょうか。
亀井 インフォメーション・ヘルスとアテンション・エコノミーの基本的な考えを踏まえて、具体的、実体的に社会や経済が動いていくことが重要です。そこは、現在の私たちの社会経済、日常生活に密接に絡んでくるところです。放送、通信、あるいは、その上に載るアプリケーション等に従事する人たちを、国家、日本社会として今後、どのような方向に持っていくかというビジョンを有していくことが大事になってくるのではないでしょうか。こうした問題を狭い憲法論に留めず、広角的に論考したのも「憲法論3.0」の特長です。
宍戸 山本先生が仰られたインフォメーション・ヘルスの話は、プラットフォーム研の『報告書』のなかでも、取り入れられていたと思います。
「憲法論3.0」に対する社会のリアクションがどうなるかはよく分からないところですが、1つは、大屋さんの議論に関連して言えば、第33次地方制度調査会等での地方制度の議論も、「憲法論3.0」の議論との連続性があるだろうということは、指摘できます。
それから、もう1つ、デジタル臨調での議論も憲法論に関わるでしょう。調査会に参加している私としては、できるだけ事務局との打ち合わせや説明の機会あるごとに、「デジタル現存在」と言うかどうかはともかく、個人の権利だとか、デジタル社会における民主主義のあり方を意識することが大事だと申し上げてきました。
さらに言えば、デジタル社会のあり方を日本国内で議論しておくことが重要です。そうでないと、国際的なデジタルエコノミーについての合意形成の場で、日本が海外から全く相手にされなくなってしまいます。
亀井 そうですね。
2.読者にも考えて欲しいところは?
■欠かせぬ国際政治と一体的な憲法論議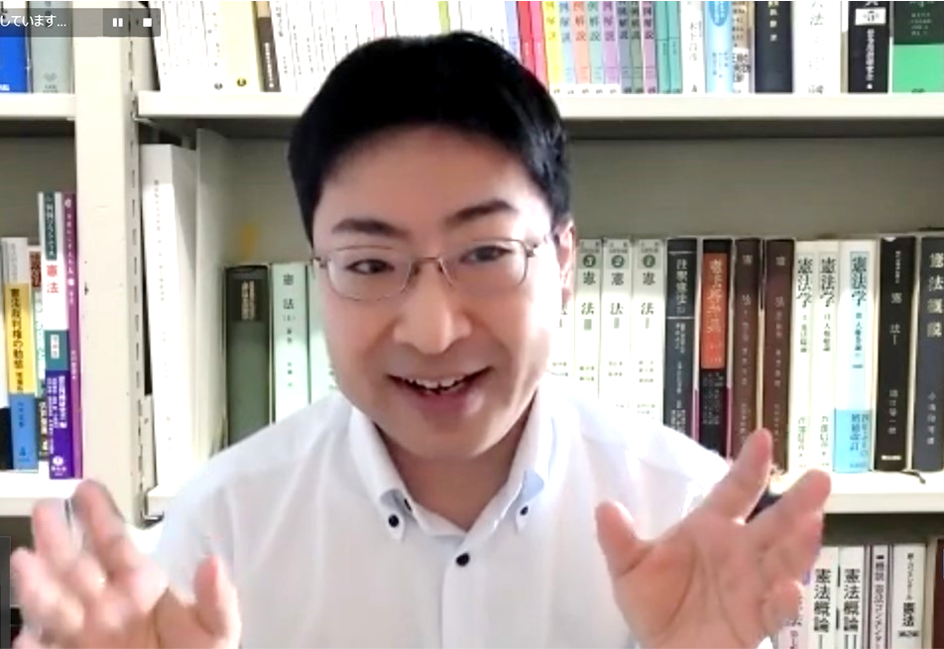
宍戸 ドイツの連立政権が昨年10月に出した『連立協定書』はまさに、私たちが提言した「憲法論3.0」のような内容になっています。デジタル時代の「民主主義」と「人権」をパワーアップさせていくために、政府はどうデジタル改革していくべきかという話になっています。「ドイツがこれをやったら、日本でもきちんと受け止めなければだめですよね」ということは、デジタル臨調でも申し上げてきました。
そして、それがダイレクトに出てきたのが、第48回G7(2022年6月)での「2022 Resilient Democracies Statement」(強靭な民主主義声明)2です。これは、明らかに議長国であるドイツの強力なイニシアチブの下で書かれたものですが、そのなかの「Global Responsibility」(グローバルな責任)では、ウクライナ問題も踏まえ、信頼できるパートナーとしての民主主義国の連帯が述べられています。また、「Information Environment」(情報環境)で、「オープンで多元的な議論を民主主義国として擁護していく」とあり、まさに山本さんが指摘された論点が述べられています。さらに、「Civil Society」(市民社会)で、「オープンで多元的な市民空間、市民の空間と市民社会を推進していく」こと、そして、「Inclusion and Equality」(包摂及び平等)が掲げられています。
日本政府はこれにサインしています。今後、日本国内のデジタル政策を含むいろいろな政治、社会経済や憲法論議においても、このような「憲法論3.0」の論点について国際合意したことを抜きに、論議はできません。「憲法論1.0」のなかにもきちんと議論すべき点はあると思いますが、こうした国際合意を無視した「憲法論1.0」は、どうしようもない話になります。
亀井 まさにそこですね。そこを通った上で「憲法論1.0」をやるのは良いけど、という話ですよね。
宍戸 そうです。まさに自国の主権を維持して、デジタルデモクラシーズのなかで、自国が尊厳をもって世界に貢献していく、そのためにわが国の文化を見直して、それをきちんと普遍的な言語で制度化するという議論であれば、健全だと思います。けれども、そうではない話になってしまっているとどうにもならないわけです。だから、我々の「憲法論3.0」とは、「憲法論1.0」や「憲法論2.0」といった狭い制度的な話を超えて、構成主義3的に、「外」の環境の部分へ目を向けていくことが大切でしょう。
このPHP「憲法」研究会はそういう議論をしましたし、逆に言えば、それは、憲法学者の専売特許ではなくて、公共政策学や行政学の人、CivicTech4の人たちとも一緒に議論していくことが大切です。なまじ「憲法論」と掲げてしまうと、「また、あの人たちが何かつまらないことをやっている」というように受け取られ、逆に、人々から敬遠されてしまう部分が生じかねません。ですから、この「憲法論3.0」をさらに外へ開いて行って、良識のある人たちが、みんなでワイワイと議論して、何かを生み出していく方向に発展していくと良いと思います。
山本 G7の話は、とても重要ですね。政府として、情報環境の再構築をどの部局で、どう受け止めて体系化していくのか。現在、総務省の「プラットフォーム研」と「放送制度検討会」では、健全な言論空間の再構築という点において、問題意識をある程度共有しているように思います。宍戸さんや曽我部さん等がこうした検討会をいわば属人的に架橋しているわけですが、もう少しメタなレベルで「言論空間をどうするの?」という課題を議論した方が良いと思います。それを受けて、各検討会で、放送はこうする、プラットフォームはこうする、という具体的な議論を重ねていった方が体系的なように思います。これは個人情報保護法制でも同じです。国際的な合意を受けて、それをわが国の法制度・法体系にどう浸透させていくのかをしっかり議論していかねばなりません。
亀井 これは、本当に大事ですね。
宍戸 そうですね。しかも、そもそも一役所がやることなのかという気もしますね。
亀井 これは、一役所のレベルではないですよね。まさにメタなところですからね。
山本 デジタル庁にどこまで期待できるのかも正直良く分かりません。最近面白いなと思っているのが憲法審査会です。意外にも、と言ったらお叱りを受けるかもしれませんが、衆議院の憲法審査会では、割と積極的にデジタルや情報環境のあり方について議論されています。オンライン国会が論点になった時もかなり実質的な議論がなされましたが、国民投票法の改正との関連で、フェイクニュースや政治的マイクロターゲティングの話もかなり活発に議論されています。憲法審査会のそういう側面を報じないメディアもまた大問題なのですが。私は、憲法審査会が、まさに「憲法論3.0」として、そのようなメタ的な議論を引き受けても良いのではないかと思います。改憲に向けたストラテジーだという誤解を解くために、憲法審査会に、たとえば「デジタル小委員会」のようなものを作って、そこで議論することを考えても良いかもしれません。
亀井 憲法論議の話はメディアが追い付いていないように感じます。憲法論議は、国際政治の枠組みと密接に繋がっていることを理解しながら、一つひとつ具体的に取り組まないといけないという大原則を理解しておくことも求められます。そうした共通理解が永田町、霞が関、その周辺でも拡がっていません。
ここには、霞が関の人材育成の問題もあるように思います。相変わらず箇所づけだけをしている国内の人と、「君、英語を喋れるよね、ワシントン行って来て」というような国際交渉を担う人が分かれてしまっていて、そこが人事でも統合されていません。両者を自由に行き来しているのはごく一部の役所に留まっています。国際政治と一つひとつの国内政治を繋げることの重要性を理解できている人材が永田町、霞が関に圧倒的に少ない状況に危機感を感じます。
宍戸 1つは、OECD等の国際機関に派遣された人材を、内政、外交両方に跨るようなところに大胆に配置ができれば、非常にポジティブな戦略ができるでしょう。
亀井 仰る通りですね。統治機構の中核である官邸では補室の問題もあります。補室において内政部門と外政部門を統合させる力、繋げる力も、より求められるようになるでしょう。
こうした問題は、先ほど、宍戸さんがお話されたG7にも繋がってきます。来年は、日本が議長国として広島で開催することが決まっていますが、その内容も、内政と外政の統合次第となってきます。
内政と外交を分けて考えるという発想自体がそもそも時代遅れになっています。補室の問題は統治機構における極めて重要な問題です。
宍戸 統治機構改革研究会の折に、牧原出さん(東京大学先端科学技術研究センター教授)が政府内に内政審議会のようなものを作ることを提言されていました。これは結構、ポジティブな戦略だと思います。外交、国際的な合意や立ち位置を内政に落として、国政のさまざまな課題を横断的に見て、国際社会に発信、転換していく装置が政府内のどこにもありません。これが大きな問題なのです。
亀井 まさに、そうですね。
宍戸 しっかりした大臣がいる状況があれば、内政と外交の接続ができるでしょう。これを小さく、デジタルから始めようとすれば、その役割はデジタル臨調やデジタル庁が担うことも考えられます。
亀井 来年のG7が1つの試金石となりますが、内政と外交を一気通貫で繋いでいく論議の行方は、海外からも見られているのではないでしょうか。その自覚を永田町、霞が関は持たねばなりません。そうなれば、「憲法論3.0」をしっかりと展望しつつ、「憲法論1.0」の議論、憲法1条や9条についても、地に足が付いた議論が可能となってくると思います。
宍戸 それで最後に収斂するのは、『統治機構改革1.5&2.0』で述べた執政論だろうと思います。「憲法論3.0」で執政の問題はスキップしたわけですが、それは『統治機構改革1.5&2.0』で一通り論じているからです。読者の皆さんにはぜひ、それらと『憲法論3.0』を合わせて読んでいただけるとありがたいですね。
亀井 そうですね。そのようなイントロダクションを私の論考で書きましたが、宍戸さんがご指摘されたところまでカバーできたかどうか…。そういう意味でも、政党はきちんとデジタル化をやってほしいし、人材育成してほしいし、内外を一気通貫でやって欲しいですね。
山本さん、宍戸さんは、内政と外交を一気通貫で考えていらっしゃいますよね。その考えはいわゆる、G7体制にも繋がっていきますし、新しい国際秩序にも直結します。そうした自覚を政治や行政を担う人たちはもちろんですが、私たち国民にもあるのでしょうか、というのは個人的には大変不安に思うところです。逆に言えば、その問題意識を持って、読者の皆さんにこの『憲法論3.0』を読んでいただけると、憲法に対する見方がずいぶん違ってくるのではないかと思います。
宍戸 そうなんですよね。内政と外交の繋がりに対する意識なく、単に憲法改正する/しないだけで提言報告書を読まれると困りますね。
亀井 「憲法論1.0」、つまり、改憲/護憲だけで読まれてしまうと、なかなかしんどくなります。「憲法論3.0」の意図を正しく読者に伝えていく工夫は、引き続き考えていかねばなりませんが、いずれにせよ、これは極めて大事な議論だと思います。
3国際関係理論の1つ。国家利益が国家間の無政府状態(Anarchy)の影響から生まれるのではなく、むしろ国家のアイデンティティー、規範から生まれ、国家間の関係が社会的な制度や歴史的な文化によって形成されていくという理論。
4シビックテック(CivicTech)とは、シビック(Civic:市民)とテック(Tech:テクノロジー)をかけあわせた造語。市民自身が、テクノロジーを活用して、行政サービスの問題や社会課題を解決する取り組みを言う。
3.最後に、読者へのメッセージをお願いします
■デジタル化で変わった憲法論議の起点 ~1.0から3.0への転回を~
山本 最初に述べたことですが、「憲法論1.0」的な議論が、メディアを含めて日本においてはいまだに強い影響力を持っていると思います。そこから自由にならない限り、先ほどの国際的なハーモナイゼーションの議論も難しいでしょう。
憲法論は、実はいろいろポテンシャルを持っていると思います。憲法改正云々だけでなく、実際の政策に対して憲法論が重要な意味を持つことがありますし、政策全体の体系性を図るという意味でも重要です。EUの全てが良いわけではありませんが、EUでは最初に憲法論があって、GDPR5にしてもDSA6にしても、具体的な法制度がそれを受け止めるかたちになっています。
日本では、政策に具体的に生かせる憲法論が少ないように思います。どうしても「改憲ですか、護憲ですか」になってしまう。いつまでもそのような議論をしていると、デジタル化を踏まえた基本的人権や統治構造のアップデートは遅々として進まず、ガタガタな環境のままで安全保障や天皇制度等のガチな論点をやらなければならなくなる。そうなると、これはカオスですよ。これまで繰り返し述べてきましたが、だからこそ「憲法論3.0」は必要なのではないでしょうか。
宍戸 広い意味で今回の「憲法論3.0」の副題には、『令和の時代の「この国のかたち」』とあります。まさに、「この国のかたち」の概念化を議論しているということです。
しかも、“この国の”と言う時の「この国」のあり方は、まさに国際環境のなかで常に考えなければいけなかったものです。それは、「この国の」という言い方で本来、意識されていることのはずです。また、そもそもの基礎となる前提が、デジタル化によって変わってくるなかで、他国との関係、あるいは、デジタル等の新しい環境を含めて、この提言報告書が「この国のかたち」を広くみんなで考える議論のきっかけになって欲しいですし、そうだろうとこの研究会メンバーは考えています。
※【前編を読む】2022年9月30日掲載
【関連報告書】
【提言報告書】PHP「憲法」研究会『憲法論3.0 令和の時代の「この国のかたち」』
<詳細はこちらから>
政策シンクタンクPHP総研
6『Digital Service Act』の略で、デジタルプラットフォームに対して、違法コンテンツ、偽情報等への対策を求めて、欧州委員会が提案した「デジタルサービス法」のこと。













