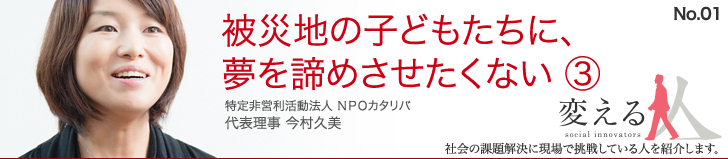私たちと地域の未来に、新しい可能性を

城山公園から見える大槌町の様子(2013.10.23撮影)
「よそから来た人」だからできたこと
地域や行政との関係で苦労したのは、決してカタリバだけではない。震災後、多くの支援団体が被災地へと向かったが、現地で信頼を得ることができず、撤退していった団体も少なくない。
「やっぱり、時間をかけて続けていく中でしか築けない信頼関係があるんだと思います。私たちの場合は、3年経って、ようやくわかってもらえてきたのかな、と。女川では、町の教育関係の委員会にも、スタッフが参加させてもらえるようにもなりました」
子どもたちに放課後の学びの場とチャンスをつくってあげたいという、ひたむきな想い。上から目線で「べき論」を振りかざすのではなく、対話と創意工夫を重ね続けてきたことが実を結んだのに違いない。加えて、地域や子どもたちの様子を、ある意味で客観的にとらえられたことも強みだったのかもしれない。
「震災にあったのが故郷だったら、逆にスタッフも私も、ここまでできていなかったかもしれません。地縁血縁のつながりがあることで利害関係が深く、多くの人に気を使わなければいけない中では、やりにくいこともありますし。外から来た人間として、多少空気を読めないところがないと、突破できないこともいっぱいありますから」
震災直後は勢いで乗り越えたところもあったが、これからのロードマップをどのように描いていくのか。今村さんはコラボ・スクールの事業としての出口戦略に、いま想いをめぐらせている。
「日本全体を見渡せば、被災していなくても、女川や大槌と同じように厳しい状況に置かれている地域はたくさんあります。今、寄付や補助金を活用しながら被災地で取り組ませていただいている中でつくったプログラムやかかわり方を、全国の類似した課題を抱える別の場所で展開できるようにしていきたいんです。そうするためには、経営的にはコストを減らして、収入を複線化することも考えなくてはいけません。例えば、コストを半分にするとしたら、何ができるか、何をしなくてはいけないのか。コミュニティの力を借りることで、新しい何かが生まれては来ないか。いろんな角度から真剣に議論しています」
モデルのひとつとして注目しているのは、10年ほど前には学力調査の結果が大分県で下から2番目だった豊後高田市。これを危機ととらえた市は「学びの21世紀塾」を立ち上げる。退職した教員や英語の話せる経営者など、「子どもに勉強を教えられる人」による講習。学校も負けじと、放課後も自習できる学力アップコーナーをつくり、まさに市全体で学習サポートに取り組んだ。すると、2006年から8年連続で県内トップクラスを守るまで、学力が向上したという。
「これはものすごいコミュニティ・ソリューションだと思うんです。関与する大人の生きがいをつくり、余暇の時間をつかって市民みんなで教育力を上げて、その結果地域力を上げている。コラボ・スクールも、たとえばいまは遠方から雇用しているスタッフを、一部現地化するとか。そのためには、まずは現地の人たちを育成するモデルに変えていくことなど、今後のかたちを多数想定して考えています」
人口が減少し、少子化も進んでいく中で、地域全体の底上げに貢献できるモデルをどのように構築していくのか。その担い手を、どうやって地元で育んでいくのか。今村さんは、すでに一歩先を見据えているようだ。