デジタル社会における憲法のあり方を考える(前編)
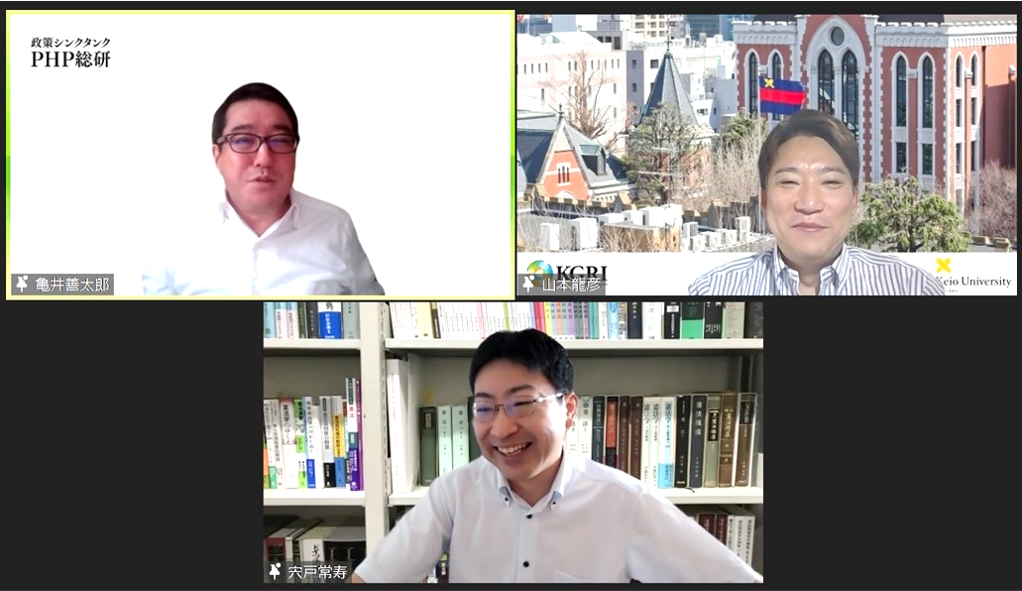
新型コロナウイルスの感染拡大、新しい国際秩序に向けた世界の動き、デジタル化、人権問題等、さまざまな問題を背景にして2022年4月に、PHP「憲法」研究会が発表した提言報告書『憲法論3.0 令和の時代のこの国のかたち』(以下、『憲法論3.0』)。
憲法は、改正の是非の議論を克服し、社会の変化にいかに応えるべきか、具体的な論点は何か、社会や政治はどのように動いていくべきか、『憲法論3.0』掲載の論考に込めた思いや考えについて、2回に分けて執筆陣が会し、議論しました。
第2回目の「前編」となる本稿は、宍戸常寿氏(東京大学大学院法学政治学研究科教授)、山本龍彦氏(慶應義塾大学法科大学院教授)に、「PHP憲法研究会の意義」「ご自身の論考のポイント、『憲法論3.0』に込めたもの」「自分以外の論考の読みどころ、新たに気づいたところ」を語っていただきました。モデレーターは、PHP総研主席研究員の亀井善太郎が務めました。
1.PHP「憲法」研究会の意義は?
■未来志向に立った憲法論議の方向性を提示
亀井 前回の座談会に続いて、今回は、PHP「憲法」研究会メンバーの宍戸さんと山本さんとお話を進めていきます。
お二人には、憲法研究会の前身の「統治機構改革研究会」にもご参加いただきました。この研究会で取り上げたのは、平成の時代に取り組まれた一連の統治機構改革でした。日本は変わらないとしばしば言われますが、統治機構は変化を遂げ、ある部分では成果をあげた一方、課題も残されています。その1つが、本来、統治機構のあり方を明記するべき憲法のあり方です。グランドデザインとしての憲法をしっかり考えていかねばなりません。この問題意識が憲法研究会を立ち上げるきっかけとなりましたし、研究会では、「令和の時代のこの国のかたち」と銘打ち、グランドデザインたる憲法というものを意識した形で検討を重ねました。
山本 提言報告書のタイトルが『憲法論3.0』となっていますが、これは、従前の憲法論議の展開、変遷からすると、大まかにこんな感じで整理できるのではないかと思い、私の方から提案しました。
まずは「憲法論1.0」。これは、日本国憲法を象徴するような規定を改正する/しないといった、イデオロギー色の強い護憲・改憲論を念頭に置いています。ここでは、特に憲法1条や9条がその対象となってきたと見ることができるでしょう。
続けて、「憲法論2.0」は、前身の研究会で検討した統治機構改革論と多くの部分が重なります。政治の世界では、たとえば1990年代の政治行政改革は「憲法論」として意識されずに行われてきたかもしれませんが、憲法研究者から見れば、「憲法改革」として捉えられる部分もありました。この「憲法論2.0」の議論でもう1つ重要なことは、いわゆる憲法附属法の存在を前景化して、「日本の憲法とは憲法典だけではない」という意識を広めたことです。憲法論議のあり方を巡る大きな動きがあったと認識しています。
日本が現在直面している課題等を踏まえれば、今後、「憲法論2.0」の密度をより高くしていくとともに、デジタル化の動きを正面から捉えた未来志向の憲法論が必要だと思います。これが「憲法論3.0」です。デジタル化には、個人と国家のあり方をラディカルに変容させる部分があるからです。
「憲法論3.0」のあり方についてはいろいろな考え方があると思いますが、「憲法論1.0」でなされたような硬直的で分断的な論議を乗り越えて行かなければならないという点については、研究会メンバーに共通認識があったように思います。
亀井 ありがとうございます。では、宍戸さん、いかがでしょうか。
宍戸 第一に、“日本が近代国家として法に基づく政治をやっていく”と言う以上、現在の高等学校公民科の学習指導要領で言うところの「公共的空間をつくる基本原理」、たとえば、法の支配、人権尊重、民主主義等が一番根っこにあり、そのことへのコミットメントは変わらないはずです。
しかし、「憲法論1.0」の時代は、その基本原理自体を咀嚼する過程でもあったのだろうと思うのです。そこには、明治憲法から日本国憲法への移り変わりをどう受け止めるのか、日本国憲法は行き過ぎで明治憲法へ戻すべきではないかということで、どうしても憲法9条と天皇制の部分、人権の制限に関する公共の福祉の強調という議論が、前面に出ていました。
その背後には、立憲主義とか近代的な国家のあり方に対するエモーショナルな反発が潜んでいたように思います。そうしたなかで「憲法論2.0」は、公共的空間を創る基本原理をどう具体化していくか、バージョンアップする議論だったと捉えています。
時間軸で言えば、1989年の東西冷戦の終結、湾岸戦争があり、国内では政権交代がありました。人口減少・少子高齢化や、日本の経済力、ファンダメンタルズの相対的な低下を見据え、強い統治機構を創らなければならないということで始められたのが「統治機構改革1.0」でした。そして、それが完全に実現していない、積み残しの部分を議論したのが「1.5」ですし、「1.0」をバージョンアップさせなければならない部分が「2.0」で、それらを合わせたのが、憲法研究会の前身の統治機構改革研究会がまとめた『統治機構改革1.5&2.0』だったわけです。
それに対し「憲法論3.0」は、デジタル社会により国家の自明性が目に見えて相対化していくなかで、公共的空間を実現する基本原理をいかに発揮するかという大きな話です。ややもすると、統治機構改革では収まらない話になるでしょう。
ここで懸念されることは、「憲法論1.0」の世界に戻ってしまうのではないかということです。天皇制の問題については、男系男子の皇位継承を維持できるかという大きな議論がありますし、また、憲法9条を巡っては、新冷戦、デカップリングの問題、それからウクライナの問題があります。
そうしたなかで、デジタル化のなかでの日本における民主主義社会、個人としての自由や利益をどう守っていくかという「憲法論3.0」に相応しい部分と、憲法は国防論議を妨げているから良くないといった「1.0」に戻るようなエモーショナルな議論の両方の可能性が考えられます。
まさに今は、「憲法論3.0」が歪な「憲法論1.0」に堕するかどうかの分岐点にあるように思います。こうしたなかで今回の提言報告書『憲法論3.0』では、健全な憲法論議の方向性を議論し、その論考を集めたことに非常に意味があるのではないかと思います。
亀井 ご指摘のとおり、「憲法論1.0」に戻る力をいろいろなところで感じます。それは日本だけの問題ではないかもしれません。世界中で法の支配や人権が揺らいでいます。
これからの議論にあるかもしれませんが、人権についての再定義や、デジタル化をはじめとする技術進化による国家そのものの相対化、そこで求められるプラットフォーマーとの対話等、様々な論点について「憲法論3.0」に向かっていかねばならないでしょう。そうしたこと無しに「憲法論1.0」に戻そうというエモーショナルな動きは常に存在し、そこに対して「憲法論3.0」が確固たるものとしてあるべきと掲げ続けることが大切です。
2.ご自身の論考のポイントは?憲法論3.0に込めたものは?
■デジタル化で高まる「言論空間の健全化」と「現存在配慮の実現」
山本 今後、安全保障や天皇の問題が不可避的に議論されることになるというご指摘はその通りだと思います。エモーショナルにならざるを得ないような論点を我々は控えている。だからこそ、「憲法論2.0」「憲法論3.0」の議論がとても重要だ、ということができます。「憲法論2.0」と「憲法論3.0」の議論を経由した天皇制論や安全保障論と、それを経由しない議論とでは、相当違ったものになると思います。「憲法論2.0」と「憲法論3.0」を重ねることで、健全な議会構造を構築し、またデジタル化をも踏まえた健全な言論空間を整備しておかないと、まともに「憲法論1.0」の議論を行うことはできません。逆に言えば、「憲法論2.0」と「憲法論3.0」を経由していれば、安全保障や天皇制についても我々はそれなりに熟慮できるかもしれない。
さて、私の論考(「デジタル化と憲法」)のポイントですが、1つは「言論空間」に関する問題です。1960年代にマーシャル・マクルーハン1 は、メディアが活字の世界からオーディオビジュアルの世界になっていくと、人間の原始的な感情や部族的な感情がもう1度、言論空間を支配することになると予言していました。
活字のメディアとオーディオビジュアルのメディアは違います。TikTokやYouTubeのようなオーディオビジュアルのプラットフォームが、特に若い世代を中心に拡大してきており、それによる思考形式の変化を考えなければならない。フェイクニュースや陰謀論の問題だけでなく、ヘイトスピーチやエコーチェンバー2 の問題も、究極的には言論空間の「構造」に関連した、人間の思考形式の変化によって引き起こされている部分があります。
こうした現状の「構造」のなかで「憲法論1.0」のようなコントロバーシャルな憲法問題を議論することは相当に危うい。これから安全保障等の問題を回避し得ないとすれば、これを議論する環境をしっかり整備しておく必要があります。言論空間の構造改革とでも言いましょうか。このような想いを、論考には込めました。
もちろん、この環境整備は主に表現の自由ないし知る自由・知る権利の再解釈によって行うことになりますが、プライバシー権の再検討も重要です。フェイクニュースやエコーチェンバーの影響力が増幅する背景には、人工知能を使ったプロファイリング技術があります。ユーザーのパーソナルデータを収集、高度に分析して、その属性や認知バイアス、政治的傾向を予測・推知し、レコメンデーションをかけていくわけですね。プライバシー権の再構成によって、プロファイリングの透明性が上がり、自己のデータに対するコントローラビリティが高まれば、商業目的のレコメンデーションや政治的なマイクロターゲティング等をある程度、川上で抑え込むことができます。
もう1つ、論考で主題化したのは、「プラットフォーム権力」です。プラットフォーム企業が、圧倒的なデータ量とアルゴリズムやAIの精度を背景に、国家権力に匹敵するような権力を持つようになっています。私は別稿で、プラットフォーム権力を、旧約聖書でリヴァイアサンと二対一頭の怪獣として登場する「ビヒモス」になぞらえましたが、現在の国際秩序はリヴァイアサンとビヒモスが対峙し、近代の主権国家体制そのものを動揺させているように思います。プラットフォーム権力をどのように統制していくのかも新たな憲法的課題だと言えるでしょう。
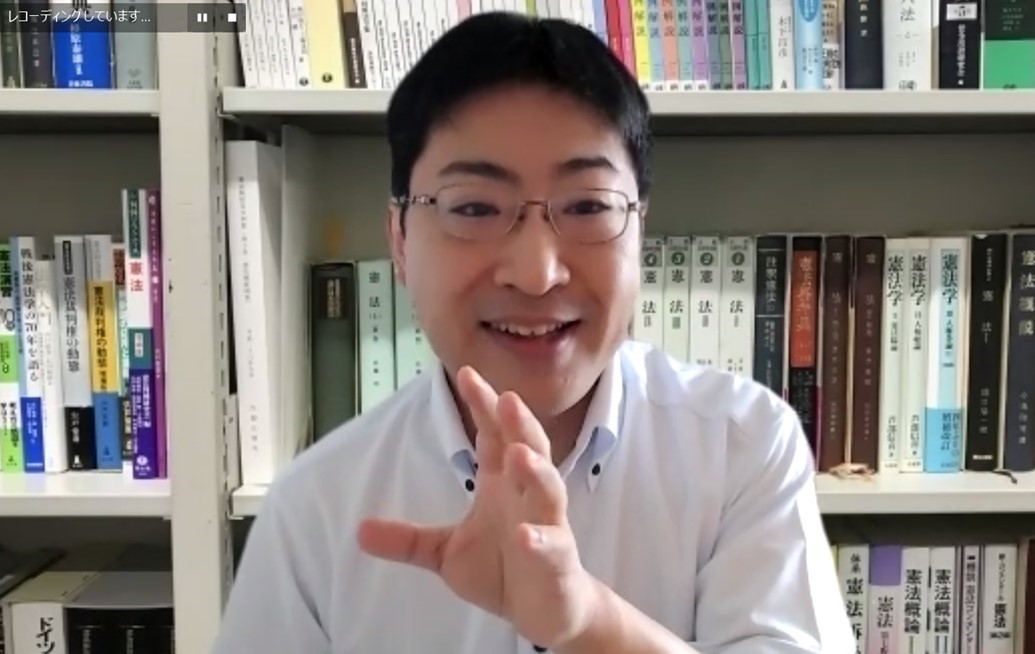
宍戸 私自身の論考(「Society5.0における立憲主義と法の支配」)のポイントの1つは、デジタル社会ですね。「憲法論3.0」が念頭に置いている、変化していく社会や国家社会のあり方は、もはやバズワード化されつつありますが、「Society5.0」の形を官民でいろいろ議論し、やってきたことにはそれでも意味があると考えていますし、この研究会では、そこから議論を始めてみたかったという想いがありました。
デジタル経済社会の捉え方に関する議論には、専らエコシステムの側から捉えていくやり方がありました。デジタル空間は、民主的な空間、水平的な社会を実現する起爆剤になることが期待されましたが、いつの間にかプラットフォーマー支配になってしまいました。そうした状況は改善しなければいけませんが、それだけであればデジタル空間の話に閉じてしまうと思います。
むしろ、曽我部さんの論考(「『個人の尊重』から見る、これからの憲法」)にあるように、伝統的な近代社会が掲げてきた個人の尊重等の社会全体をどうガバナンスしていくかという観点から、「憲法論3.0」が前提する社会の変化を捕まえ、それと法の支配や権力分立の原理をくっつけて議論を試みたのが私の論考のポイントです。経済社会の問題をガバナンスの変化のなかに取り込むため、少し強めに「デジタル現存在配慮」という概念を出してみました。
「現存在配慮」3 は、もともとドイツの行政法にあった議論で、資本主義後期以降の国家のガバナンスの課題を問題としています。どのように受け止めるか難しいところもありますが、私は、社会と国家を支える個人の自律的で多様な能力と意思と、現実の生活環境や状況とのズレを、国家が自らの活動で埋める作業のことを、広く「現存在配慮」と考えています。たとえば、都市の道路や水道の運営、鉄道等の移動や輸送手段の確保、さらには社会保障制度を含む多様な仕組みを、国家が直接的、間接的に確保することを含みます。
一方で、現存在配慮の実現のために強くなり過ぎてしまいかねない国家を法により統制するために、人権論の根っこの部分とガバナンスの話をくっつけてみました。さらに、「デジタル現存在」という形で、デジタル化した経済社会システムのなかで生きる個人の生存を考えました。そのことで、デジタル現存在を実現すると同時に、国家権力が強くなり過ぎないようにするためのガバナンスとして、法の支配や権力分立のバージョンアップを論じてみました。
研究会でも、現存在配慮に偏ると、世代間公平や、中長期的な国家政治における公共の実現が霞む可能性があるとの指摘を大屋さんから受けましたが、それはその通りだと思います。ただ、この提言報告書にはいろいろな論考があり、そのうちの1つとして読んでいただくのが良いのではないかと思っています。
亀井 「デジタル現存在」への配慮については、研究会でも盛り上がった論点でした。ご指摘の通り、現存在配慮の実現のために強くなりがちな国家の統制について、これからのデジタル化した経済や社会のなかでいかに実効性あるものとしていくのか、といった論点はもちろんのこと、そもそも、現存在配慮の拡大によって、未来に生きる人たちへの配慮が欠けてしまいがちとの意見も交わされました。今生きている人たちで意思決定を行う民主主義の限界を考える、ある意味、統治構造にも直結する問題提起だと思います。宍戸さんに示していただいた配慮すべき「デジタル現存在」という概念は、新しい憲法のあり方を考えるきっかけをもたらしてくれていると思います。
山本さんの論考では、デジタル空間へアクセスできないと、そもそも現代社会では理想を達成できない人たちが出てくるという指摘がありました。アクセスするための必要最低限の機器や通信を人々に付与するところまでを考えなくてなりません。ただ、これも誤解されがちですが、付与すること自体は目的ではありません。ハードウェアとか5G云々ではなく、「デジタル現存在」への配慮を実現するための手段であり、その根底にある憲法論が大事なポイントだと思います。
山本 現存在配慮の箇所は、興味深く読ませていただきました。デジタル空間への接続の自由、接続可能性は、単にデバイスを提供すれば良いという話ではありません。デバイスの提供を前提とした上で、考えるべきなのは、結局、人間間の関係性だと思います。
論考(「Society5.0における立憲主義と法の支配」)のなかで、宍戸さんが「デジタル基本権」の確立を提唱されていますが、私も強く賛同します。今年1月に、欧州委員会が『The Declaration on Digital Rights and Principles』(デジタル権利と原則に関する宣言)4 を出していますね。この宣言の第2章に「連帯と包摂」という章があります。このなかで、接続可能性とかデジタル教育、就労環境、労働の問題が明記されていますが、この辺は、先ほどのデジタル現存在と関連しているように思います。
1つ気になるのは、この現存在配慮を政府や政治家がどのくらい真面目に受け取ってくれているのか、あるいは、受け取るのかということです。今後、どういうルートでこういう議論を喚起していくのが一番合理的なのかを検討していかなければならない。手続的な検討が必要ということです。論考(「デジタル化と憲法」)では「ロトクラシー」5 の話にも触れました。現存在配慮はやはり、市民の声をしっかり反映していかなければならない。デジタル庁等では、「誰も取り残さないデジタル化」と謳っていますが、どうしても、効率性や経済合理性を重視する、インフラやイノベーションの話が中心になってしまい、市民のリアルなニーズを汲み取っていくことが難しくなっているように思います。これでデジタル現存在はまじめに議論されるのだろうか。この問題は、統治構造や政治過程論にダイレクトに関わりますね。
現在の統治構造ですと、デジタル人材交流等で官民連携は進み、そこに専門家等も関わっていくのですが、どうしてもビジネスの視点が強く出てしまう。デジタル専門性という観点で「民」を頼らなければならないので、官民が「協働」のかたちをとることになる。それ自体は悪いことではないのですが、それにより官が、「パートナー」である民間企業に忖度するという構造ができてしまいます。プラットフォーム企業によるロビイングの影響力も強いと言わざるをえません。
こうした政治過程では「市民」の視点が政策にうまく反映されず、デジタル現存在はどこかに行ってしまう危険があります。論考では、デジタル政策をバランス良く進めていくための1つのツールとしてロトクラシーに触れました。市民の声のフィードバックという点では、「デジタル臨時行政調査会」(以下、「デジタル臨調」)等にも期待しています。
現存在配慮に関してもう1つ気になっているのが、現在のプラットフォームのビジネスモデルが、いわゆる「アテンション・エコノミー」6 になっているということです。そこでは、ユーザーの認知プロセスに介入して、エンゲージメント(ページビューやサイト滞在時間)を強引に獲得することが行われています。
心理学の二重過程論によれば、人の思考には「早い思考」と「遅い思考」の2つのモードがあります7 。前者が「システム1」、後者が「システム2」ですね。アテンション・エコノミーの世界では、熟慮型のゆっくりとした思考モードであるシステム2を抑制して、生理的で直感的・反射的な思考モードであるシステム1を刺激してエンゲージメントを高める、アディクション(依存・中毒)の状態を作り出すことを行っていると言われています。ここでは、国家がそのような状況に対して何もしなくて良いのかが問われる。プラットフォーム上では、システム1が常に刺激されて、我々は瞳孔が開きっぱなしの状態にさせられているわけですね。常に興奮状態にあると言って良い。言論空間への国家の介入には十分な注意が必要ですが、そうした状況に対し国家が一定の役割を果たすことが、個人の尊厳や現存在配慮との関係では非常に重要なのではないでしょうか。
最近、東京大学の鳥海不二夫さん(計算社会科学)と、「情報的健康」(以下、「インフォメーション・ヘルス」8 )というコンセプトの重要性を主張しています。これは、現状のアテンション・エコノミーの世界では、商業的アルゴリズムにより、その人がクリックするであろう同質の情報ばかりがレコメンデーションされ、情報の「偏食」が起きているのではないか、それによりフェイクニュースや誹謗中傷投稿等への「免疫」が失われてきているのではないか、という問題意識を前提としています。このインフォメーション・ヘルスは、さまざまな情報を主体的に摂取できる「知る自由」(憲法21条)と関連しているだけでなく、「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」とする生存権(憲法25条)とも関連していると考えています。この「健康で文化的な」という文言をデジタル社会においてどのようにアップデートするかという論点も、現存在配慮との関係で重要になるかもしれませんね。
宍戸 デジタル社会において、国家がデジタル空間をハード、ソフト両面できちんと健全なものとして機能させ、人々がアクセスできるようにすることは、大きな課題です。
デジタル現存在の裏側にあたる話として、これまでの国会や社会は、その時点での使えるリソースないしテクノロジーで、人間を規格化して捉えていました。たとえば、生活保護について幾つかの扶助の類型を作り、そこに当てはめて給付したり、「この地域は過疎地だから」という粗い形で社会や人びとを把握したりして、それに対して、国が一定の手を打ってきました。
その最たるものが、社会保障における標準世帯のイメージです。しかし、そうした規格化が却って制度に死角を生じさせたり、人々の行動を歪めることがあります。たとえば、世帯の女性がパートで働く時に、一定の時間以上働くと税制上不利になるから働かないといった類です。国家による法規制が「アーキテクチャー」として人々の行動可能性を制約し、やがて、それが「合理的」な行動だということになって、全体最適ではない世界を生み出してしまっています。
私の頭のなかには、一度、国民一人ひとりを理想的な「個人」たらしめる政策をガッチリ実施できる「国家の能力」と、そこに参画する「個人の手続的な地位・権利」を構想した上で、“本当はそこまでできないよね”とか“管理社会は怖いよね”“この辺でやめようね”といった落とし所を考えたら良いのではないか、という考えがあります。
それと別に、山本さんの論考にあるロトクラシーに対しては、私はややネガティブなイメージを持っています。根本的には、提言報告書で論じた「rightnessとlegitimacy」9 をそれぞれに確保する、代表制民主主義を活性化させるという面では、ロトクラシーにはポジティブな面があるとも思います。反面、ロトで当たる人は、確率からして、先ほど申し上げた意味で「標準的」な人々が多くなるでしょう。本来、政治が配慮すべき、政策のサポートを必要とするマイノリティの声が上手く政治に反映されるかどうかは分からないと私は考えています。
ではどうするのか?という話ですが、目の前の問題について言えば、私は、曽我部さんが論考(「『個人の尊重』から見る、これからの憲法」)で書かれている「請願権」の現代化をデジタル技術で行なったり、規格上、困っていることが見えているが施策を打たれていない人たちに対応するため、内閣府共生社会部局をデジタル庁にくっつけて、子どもや女性、外国人問題をデジタルで一気にやってしまったら良いと思います。それが最初の戦略ではないかと思います。
2似た考えを持つ者同士がネットワーク化することで、その考え方が相互に響き合い、過激化していく現象。
3現実社会のなかで「個人」の理想をある程度実現するための国家の統治活動と定義される。詳しくは、提言報告書『憲法論3.0』(pp.18)を参照。
4欧州委員会が欧州議会および欧州連合(EU)理事会に対し、欧州がどのようなデジタルトランスフォメーション(DX)を促進し守ろうとしているのかについて、明確な参考基準を示すことを提案した宣言(2022年1月26日)。プレスリリース(日本語訳)は、https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_452
5Lot(抽選、くじ引き)とCracy(政治、支配)の造語。選挙ではなく、「くじ引き」で議員を選ぶという、「抽選制」民主主義の構想である。ロトクラシーは、選挙による民主主義とは異なり、一般市民から無作為抽出で議員を選ぶことで、一般市民の声を等しく政治に反映できるとされる。
6「関心」や「注意」を競う経済のこと。人々の関心や注目の度合いが経済的価値を持ち、貨幣のように交換材として機能する状況を指す。プラットフォーム事業者は行動履歴を取得することで、利用者の関心を強奪できるようになっている、とされる。
7ノーベル経済学賞を受賞した行動経済学者であるダニエル・カーネマンの著書『ファスト&スロー』で広く知られるようになった。人間の思考モードは大別して、2システム(情報処理モード)があり、これらを合わせて二重過程理論等と呼ばれる。
8情報空間のビッグバンとパーソナライズ化のなかで、ユーザーの興味関心に合った情報だけでなく、多様で幅広い情報に触れることで、情報摂取の偏り(不健康)が解消されている健康な状態を言う。
9legitimacyとrightnessは政治における2つの正しさのこと。つまり、国民によって選ばれたという legitimacy(みんなで選んだという「正統性」)と、社会として合理性や専門性に基づいて正しい選択がされるという rightness(専門性や合理性に基づく「正当性」) を指す。2つの正しさが同じ場合もあれば、異なる場合もあるが、いずれも尊重し、相克させながら、それぞれを高めていく必要がある。日本の平成期の一連の統治機構改革では、国民が選んだ内閣が統治機構の主体となったため、legitimacyに傾く動きが見られている。
3.自分以外の論考の読みどころは?新たに気づいたところは?
■新しい憲法論議に不可欠なインフォメーション・ヘルスの確保
亀井 新しい技術をうまく活用することを通じて、ひとり一人の人権とまさに開かれた公共を調和させることができる社会を目指すのがSociety5.0の概念です。この点に関しては、先ほど宍戸さんはバズワード化しているかもしれないと仰っていましたが、私たちはSociety5.0で何を目指したのか、あらためて確認することが大切です。
「個人の利益」といっても、これまでの社会では性別や年代といったステレオタイプ化された区分けの下で認識されていたに過ぎません。これからの社会では、デジタル化の活用によって、まさに現存在を尊重できる社会がすぐそこにまで来ているようにも思います。
地方自治体では、先ほど、山本さんが言われたロトクラシーが進んでいます。とはいえ、くじ引きで議員を選ぶのではなく、新しい施設整備の意見、既存の行政事業の評価・改善といったプロセスにおいて、住民基本台帳から無作為抽出された市民が代表として、そのプロセスに参加するというかたちです。私自身も、そうしたプロセスに専門家の立場から関わった経験がありますが、ロトクラシーは、地方自治体の硬直化した課題に対応する大きな効果があります。
また、ロトクラシーではありませんが、司法制度改革によって導入された裁判員制度によって、市民が刑事裁判に裁判員として参加するようになったことで、警察の捜査は科学的なエビデンスを以前よりも収集するようになりました。
一方、先ほど、宍戸さんが指摘されたマイノリティへの配慮は専門家がまさに担うべきところで、これは十分に留意しなければならないところでしょう。また、これも先ほど議論のあったように国政レベルにおいてエモーショナルな判断になりそうな政策課題にロトクラシーを入れるには、事前の情報共有や専門家による分析の提供等も含め、何らかのレイヤーが必要だと思います。
近年の政治や社会の動きを見ていると、日本に限らず、早い思考、システム1が優勢です。しかし、自分自身の思考をあらためて振り返ってみれば、最初から賛成や反対を決めて意思表示に臨むというのはなかなか難しいことです。この点について、そういうのが得意そうなアメリカ人と話してみたことがあるのですが、彼らも、最初から賛成や反対を決めるのは苦手だというのです。むしろ、誰かの考えや意見に耳を傾けながら、あるいは、実際の当事者の声を聴くことによって、判断が変わることもあるでしょう。まさに、遅い思考であるシステム2が動き出すきっかけが必要なのです。
そうした意味で、社会の意思決定のためには、お互いの考えや意見が言える場、そして、見える場、ある種のアゴラが必要なのではないでしょうか。党派争いのために対立し、なんでも主張し合うのではなく、また、自分の利益ばかりではなく、社会全体の利益を考えることができ、人の本来の社会性の源泉でもある相互扶助を実践することができる、そうした社会参加の場が必要なのだと思います。第1回座談会でも出ましたが、PoliTechの設計においても必要な考え方です。
山本 アゴラの必要性については強く同意します。フィナンシャルタイムズの記者であるジェマイマ・ケリーは、SNSを中心とする現在の言論空間を、市民が意見交換を行う公共的なアゴラではなく、観客がよく暴徒化した激情的な「ディオニソス劇場」になぞらえています。この劇場は、ディオニソスを祝すディオニューシア祭の会場となった場所ですが、言うまでもなくこのディオニソスは、葡萄酒と酩酊の神だったわけです。言論空間全体がディオニソス化するなかで、市民的な議論空間であるアゴラをいかに構築するかは、極めて重要な課題です。曽我部さんが論考で提案された「デジタル請願権」もそのための1つの有力な手段になりえます。ただ、デジタル請願権の実現にはいくつかの困難もあるでしょう。たとえば、請願者の同一性をいかに担保するのか。これは技術的に解決できるのかもしれませんが、エコーチェンバーの影響でシステム1を刺激された感情的、部族的な「請願」をどのように取り扱うのかも難しい。これを全面的に認めると、ディオニソス劇場がむしろ政治に直結することになってしまいます。
いずれにせよ、国会をどのようにナッジ10 していくかという曽我部さんの問題意識には共感を覚えます。本来、参議院がシステム2の部分を担うことが期待されているはずなのですが、なかなかそうなっていない。そのなかで、議会での熟議をどのようにナッジしていくかが重要です。
亀井 そうですね。システム1をヒートアップさせるのではなく、システム2を稼働させる、そういうPoliTech、そして、現実の政治の対応が求められますね。これからのデジタル技術の発展にも依るでしょうが、賛成/反対の対立を煽らず、どちらも合意できることを見えるようにしていく工夫も必要でしょう。テキスト分析をAIでやれば、かなりのところまでできるようになるはずです。
山本 「憲法論3.0」はそういう話にもなると思いますね。カナダの哲学者ジョセフ・ヒースは、最近「啓蒙主義2.0」を唱えていますが、それは、理性を個人の頭のなかに存在するものと捉えた古典的な啓蒙主義を批判し、理性をある種の社会的事業として捉えます。理性は単独で行使されるのではなく、制度的な支援を得て社会的に共同行使されるのだと。そのためには、「対話」を促すための技術やアーキテクチャーを構築・設計していくことが重要で、技術系の専門家とのコラボレーションも必要になると思います。
亀井 そうですね。私たちはそういう人たちとも話をしなければいけないでしょう。
宍戸 国民の公共空間への参加に繋げて、個人のイメージについて話したいと思います。先ほど、亀井さんがアメリカ人の話をされましたが、そこで言うアメリカ人は、「正しく説得するし、正しく説得される気概を持っている人間」がイメージされていますね。
亀井 たしかに。仰る通りですね。
宍戸 山本さんが仰る「遅い思考」であるシステム2は、そこがポイントですよね。日本の政治の場では、システム2に対応する対話が大きくスキップされています。たとえば、統治機構改革論において、小選挙区制で政権交代を目指すことそれ自体は1つのモデルで良いと私は思いますが、最後の投票に至るまでのプロセスや、投票で選ばれた国会議員の活動や政治活動一般はシステム2、集合的に正しく説得されるための対話の部分がしっかり機能しないと、ただ「白黒付けました」というシステム1だけになってしまうのではないでしょうか。
亀井 まさに。そこはすごく大事なところです。
宍戸 イギリス政治もブレグジットをやるぐらいですから、システム2が決して万能とも思わないのですが、少なくとも議会のなかでどういう議論があり、政官が動いているのかということが見えることは大切です。
その観点で上田さんの論考(「日本の統治構造とウエストミンスターシステム」)が提起した問題は、ウエストミンスター・モデルを日本で取る/取らない、良い/悪いではなく、大事なことは、イギリスのモデルには集合的にシステム2をやろうとする仕掛けが内在しているけれども、日本には何も無い、あるいは、見えない部分でシステム2をやっているということをどうするかだと思います。
それから、個人、有権者の投票ばかりが問題になりますが、その手前で、候補者を見たり、自分が候補者に働きかけたり、候補者と考えを投げ掛けたりする議論こそが大切でしょう。アメリカのプライマリー11 のようなしくみは、本来的、理想的に機能すれば、有権者と候補者が対話するなかで、政策や候補者同士が連携したり、議論を収斂させる過程になり得ると思うのです。
そのプライマリーが今、トランプ現象のあおりで、システム1的に党を乗っ取るための手段として使われてしまっているように思います。山本さんが仰ったように、認知科学的な話、PoliTechな話と、あるべき集合的な意思決定を、しっかり結びつけた議論をすることが重要です。
亀井 極めて重要なポイントですね。日本の場合で考えてみますと、そこで問われるのが、先ほど、山本さんもお話された参議院の役割です。参議院が中央と地方の調整を担うことや、院内に独立財政機関を設置することを目指すべきではないでしょうか。ここは二院制の意義にも適合します。
システム1とシステム2の議論で言えば、第一院である衆議院は内閣に近いですから、どうしてもシステム1的な判断に寄っていきます。一方、これから起きてくるであろう天皇制に関わる議論であるとか、新しい国際秩序についても、民主主義/非民主主義、法の支配/人の支配といった議論を、早い思考であるシステム1で、エモーショナルに進めてしまうのは危なっかしいことになります。
それこそ、統治機構のあるべき姿を探求する「憲法論2.0」、また、デジタル化等の社会の変化を捉えた「憲法論3.0」をしっかり踏まえて、私たちの統治機構のなかで、誰がどこでシステム2を駆動させるのか、そこをしっかり自覚しておかねばなりません。統治機構改革研究会でも、政府、議会、政党、それぞれにおいて中長期の検討や議論が不在となってきたことを大きな課題として提起しました。これにも繋がる話ですね。
宍戸 社会全体がシステム1に寄ってきている要因の1つは、プラットフォームサービスのあり方による部分も大きいのではないかと思います。それは、山本さんが指摘された2つ目の論点ですね。
山本 全くその通りです。legitimacyとrightnessの関係も、意外なほどにシステム1とシステム2の関係に似ています。
亀井 そうですね。
山本 結局、1990年代の政治改革では、システム1寄りの、非常に分かりやすい直線的・単線的な政治が目指されました。その流れとプラットフォームのビジネスモデルとが合流しているのが現在の政治社会状況です。プラットフォームの台頭により、労働組合やマスメディア、さらには政党のような中間集団、言わば強制的に作動してきたシステム2が弱体化し、すべてがファスト化しています。システム1的な世界にグッと引き寄せられている状況とも言えます。これはよろしくない。
そこで、「何とかしなきゃ」と考えて出てきたコンセプトが、先ほど申し上げたインフォメーション・ヘルスなのかなと思います。食事のアナロジーで考えることには批判もあるでしょうが、さまざまな食材を、バランス良く、ゆっくり噛んで食べるというのが健康の秘訣だとすれば、情報についても同じことが言えそうです。「タイパ」(タイム・パフォーマンス)が重視されるように、「デジタル」と「ファスト」との相性が良いのに対して、「デジタル」と「スロー」とは相性が良くないと考えられてきました。しかし、その発想には一部修正が必要でしょう。テクノロジーは、熟慮の再現を目指すものでもなければならない。政治過程に目を向けても、ロトクラシーや請願権、さらには参議院改革、独立行政委員会等、legitimacyと直結する単線的でファストなものを抑制する「政治のシステム2」を積極的に駆動させることが必要になると思います。
亀井 本来、rightnessを担うべき官僚機構が、legitimacyと直結する単線的でファストなシステム1に引きずられているのも問題です。本来、彼らは高い専門性を持って、一つひとつ丁寧に行政を動かしていかねばなりませんが、政治からは「それでは遅い」とか「そんなことは要求していない」と怒られ、メディアからは「失敗した」と叱責され、自分たちは何をしていけば良いのかが分からない状態に陥っています。システム2を駆動させる意義や方法論には、そんな彼らの専門性の回復のヒントがあるかもしれません。
※【後編を読む】2022年10月7日掲載
【関連報告書】
【提言報告書】PHP「憲法」研究会『憲法論3.0 令和の時代の「この国のかたち」』
<詳細はこちらから>
政策シンクタンクPHP総研
11予備選挙(primary election)のこと。














