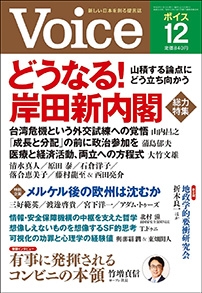情報・安全保障機構の中枢を支えた哲学
内閣情報官を歴代最長の7年8カ月ものあいだ務め、国家安全保障局長として同局経済班を発足させて経済安全保障政策を推進するなど、情報部門と政策部門それぞれのトップを歴任した北村滋氏が語る、日本のインテリジェンスの真実の姿と、我が国が置かれている状況と課題
NSC/NSS設置などで「普通の国」に
――(金子)北村さんは、我が国の情報機関の要である内閣情報官と、外交・安全保障政策の司令塔である国家安全保障局長(NSS局長)をそれぞれ務めました。福澤諭吉の言葉「一身にして二生、一人にして両身」を体現するようなキャリアですが、第二次安倍政権以降の情報と政策の関係性をどう振り返りますか。
北村:NSC(国家安全保障会議)が創設されたのは第二次安倍内閣でしたが、これが画期的であったことは間違いありません。また、2014年1月にはNSCの事務局として内閣官房にNSS(国家安全保障局)が発足したことで、NSCが政策決定に向けてより綿密に準備ができるようになりました。
具体的な変化を申し上げれば、以前は安全保障といえば外務省と防衛省とが個別に対応していましたが、NSSが設置されて以降は、政府が一体となって取り組んでいます。また、政策サイドから情報関心が示される機会が増えたことで、提供すべき情報について各情報機関の理解が進みました。かように情報サイドと政策サイドの連携が深まったことで、政府内の安全保障の位置付けが圧倒的に高まり、あえていえば「普通の国」に近づいたという感を抱いています。
加えて安倍内閣時代の大きな変化としては、2013年12月の特定秘密保護法の制定が挙げられるでしょう。イージス艦関連の情報が漏洩する事件もあったように、それまでアメリカをはじめとするG7諸国等には、我が国の情報当局と情報をやり取りする際には、一定の懸念が存在していました。実際に同盟国であるアメリカから改善を要請された場面も多々あり、同法の成立により遅まきながら機密情報を守る枠組みができたと言えるでしょう。
――北村さんが上梓された『情報と国家』(中央公論新社)を拝読すると、内閣情報官就任前から情報コミュニティという概念に着目されていたことがよく分かります。現在の日本の情報コミュニティをどう評価しますか。
北村:たとえば、内閣官房副長官をトップとした合同情報会議は、かつては2週間に一度、現在ではほぼ毎週行なわれており、そこには政策サイドのNSS局長や内閣危機管理監も出席しています。その他の内閣情報会議や下位の課長級の分析会議にも政策サイドの人間が出席するなどマルチレイヤでやり取りが行なわれており、インテリジェンス・サイクルが活性化されていると評価できます。
――NSCやNSSが発足する前後では、インテリジェンス・サイクルは明確に変化したのでしょうか。
北村:私は、確実に変わったと実感しています。たとえば内閣情報調査室とNSSはいまや相互不可欠の関係ですし、情報サイドから政策サイドへのブリーフ(報告)も分野を問わず頻繁に行なわれ、然るべき材料も提供されています。内情を知らない人が傍から見る以上に緊密に情報提供や政策調整がなされています。
――私も第二次安倍政権の「国家安全保障会議の創設に関する有識者会議」の末席でNSCの制度設計に関わりましたが、当時はNSCが情報収集まで行なうのでは、との議論もありました。この点に関してはどうお考えでしょうか。
北村:情報サイドと政策サイドの両方に身を置いた人間として言わせていただくならば、実際にNSCが情報収集のオペレーションまで行なえるかといえば、物理的にも、体制的にも、そこまでは到底手が回りません。たしかに情報収集・分析と政策決定は切っても切れない関係ですが、現実には異なる世界であり、明確に分担すべきです。
――結論としては、NSCやNSSが設置されてから情報コミュニティが本格的に強固になったという認識でよろしいのでしょうか。
北村:「本格的」という言葉が相応しいか否かは私には分かりかねますが、政策部門から情報関心が明確に示されるようになり、それに基づいて情報収集が行なわれる流れは確実に形成されています。
官邸は「裁断の場」
――北村さんは2019年9月に第2代NSS局長に就任されました。情報サイドから政策サイドに移ったことで、あらためて気づいたことはありましたか。
北村:いえ、とくにはありませんでした。私自身、組織の仕組みや自身の役割が大きく変わることは充分に理解していましたから。ただし、情報サイドの報告に対しては、なるべく真摯に聞く姿勢は堅持しました。情報サイドがどんな意識で情報をもってきて、いかなる見方をしているのか、都度かなり詳しく聞きました。
――政策サイドが情報サイドに対してフィードバックすることも大切だということですね。
北村:おっしゃるとおりです。フィードバックは、とても重要です。上がってきた情報が役に立ったか否か、さらにはどんな情報に政策決定者は関心を示したかを情報サイドに伝えることで、インテリジェンス・サイクルの精度は確実に高められます。
――メディアのなかには、NSCは安倍(晋三)総理だから、NSSは谷内正太郎・初代局長だから上手く回っているのだと報じる向きもありました。谷内さんからNSSを引き継ぐうえで特別に意識されたことはありましたか。
北村:谷内前局長と比較して独自性を出そうという考えは毛頭ありませんでした。私は役人ですから、事務の継続性がもっとも重要であることは十分に認識しています。トップに座る人間によって制度や方針が180度変わることは、とくに行政機構としては宜しくありません。引き継ぎの際に意を用いたのは、あくまでも谷内前局長が確立されたNSSの行政制度や慣行を継続することでした。もちろん引き継いだ後にトライ&エラーを重ねて微修正することはありましたが、それも谷内前局長時代からの連続性の延長線上にあるものばかりでした。
――北村さんは安倍総理と菅(義偉)総理それぞれのもとでNSS局長を務めました。2人のNSC運営に違いはありましたか。
北村:安倍総理にも、菅総理にも、頻繁にNSCを開いていただいた点は共通しています。菅総理とのやり取りを思い返せば、安全保障政策をとくに重視され、じっくりと考える方であったと記憶しています。ですから私は、NSCで議論する前に菅総理からあらかじめ問題意識を伺い、それを受けて会議でどのような素材を出し、議論していただくかをつねに吟味していました。
――アメリカでは大統領が代わるとNSCやそのスタッフ組織の機能が大きく変わります。安倍総理から菅総理に交代した際には大きな変化はありましたか。
北村:菅総理は、大方針として就任前から安倍政権からの継続性を主張されていました。NSC運営においても、前例を尊重されていたように思います。
――NSC/NSSの設置や情報コミュニティの強化は間違いなく国益に適うことです。しかし、他方で「なんでも官邸団」と揶揄する言葉もあり、たとえば防衛政策など省庁レベルでオーナーシップをもって取り組むべきものまでもが官邸任せに陥っていると懸念する声もあります。
北村:少なくとも、私がNSS局長を務めていた2年間で、関係省庁との間に意志疎通で齟齬が生じたことはありませんでした。例に挙げていただいた防衛政策について言えば、防衛省や外務省の俊秀が官邸側にもたれかかるようなことは一切なかったと記憶しています。
――北村さんからご覧になって、官邸とはどのような意味や意義をもつ場所でしょうか。
北村:ひと言でいえば「裁断の場」です。要するに物事を決する場ではないでしょうか。それは、すなわち政策決定の場という意味です。だからこそ、判断の前提となるインフォメーションやインテリジェンスが必要となるわけです。私は情報サイドと政策サイドの両方に身を置いた人間ですが、どちらの立場においても、「裁断」が円滑に進むように取り計らうことが使命だと考えていました。
「憲法は変わる、されど行政法は残る」
――『情報と国家』では、情報機関や総理と警察との関係などについて日本の独自性や歴史的経緯をふまえて考察されている点が印象的でした。
北村:私は学生時代には行政法を学んでいましたが、我が国の現代行政法に圧倒的な影響を与えたのは19世紀から20世紀にかけて活躍したドイツの法学者であるオットー・マイヤーです。彼はドイツ帝国憲法からワイマール憲法に変わったとき、「憲法は変わる、されど行政法は残る」と語っています。学生時代、雄川一郎先生の初回の講義の板書でこの言葉を知り、最初はあまりに衝撃的で意味が良く分かりませんでした。教養学部の法学授業では、伊藤正己先生から「上位法は下位法を破る」と学んできたばかりでしたから。その後、行政に実際に身を置き、政体を定める憲法が変わったとしても、制度自体の継続性は一定限度残るということではないかと思うようになりました。
我が国の歴史を紐解いても、戦前から終戦、占領期、戦後という流れのなかで、行政制度は外的な要因で断絶と空白をもたらされつつも、省庁における人的構成の継続性や新たに構築される行政制度のモチーフにおいて過去との連続性を看取することが可能です。情報機構においても、かかる側面は確実に存在すると思います。
国家において情報がどう位置付けられてきたかについて、絶えず問題意識を抱いてきました。各国のインテリジェンス・コミュニティの在り方もまた、それぞれの歴史から規定されると考えています。拙著で取り上げたフランスにおいても、情報と国家との関係性を考えるうえで日本とは全く異なった発展の道筋を辿っています。しかしながら一方で、たとえば政策決定者への情報の統合といった側面において、我が国と共通する現代的問題性を抱えているのは興味深いことです。
――いまお話しいただいたように、フランスを参照軸にされている点は実に興味深く感じました。日本ではこのようなテーマについては、往々にしてアメリカやイギリスが例に挙げられます。
北村:戦前の日本で言えば、たとえば警察制度などは中央集権的なフランスを参考にしていました。とはいえ、同国の歴史を振り返ると、先の大戦では実際にはドイツに蹂躙された敗戦国だったはずが、ドゴール将軍がイギリスで亡命政府を樹立したこともあり、最終的には戦勝国になった。かかる経緯もあり、フランスは、我が国のように「敗戦」に基づいた大きな組織的変動を経ていません。フランスは私が留学した地でもありますが、日本とは異なる歴史的経緯をもつ国の行政制度を勉強できたことは、個人的にも非常に有意義でした。
――フランスの行政制度には具体的にどのような特徴があるのでしょうか。
北村:有数の官僚国家ですから。セクショナリズムが強く、行政制度がかなり堅固な国だと評価できるでしょう。国防省や警察組織を擁する内務省がインテリジェンス面で大きな役割を果たしています。一方でNSCのような組織はありません。じつのところ、情報の統合に関しては決して成功しているとは言えないと思います。世界的な趨勢としては、アメリカではDNI(国家情報長官)、オーストラリアではONI(国家情報庁)が置かれているように、それぞれの機関がバラバラに政策決定者に情報を上げることなく、情報を統合する部門が精査することの重要性が認識されつつあります。
経済安全保障時代に求められるインテリジェンス能力
――今後、我が国のインテリジェンス体制をどのように深化させていくべきだとお考えでしょうか。
北村:一つの鍵となるのは法制度の整備ではないでしょうか。たとえば、関係省庁から情報を上げてもらう際に、現在は「お願いベース」ですが、本来であれば提出義務が確保されるべきです。誰が内閣情報官に座ろうが関係省庁から的確に情報が上がるべきであり、そのようにファンクション(機能)させるには内閣法の改正なども視野に入れる必要があります。
――情報の質の重要性についてはどう認識されているでしょうか。インテリジェンス研究では、エビデンスや論理に基づいた情報をもつことが、「情報の政治化」を防ぐ最大防波堤であるとの議論もあります。
北村:情報を分析する側からすれば、虚偽情報は、およそ見分けがつきます。2010年、尖閣諸島近海で中国の漁船が日本の巡視船に衝突した際、CCTV(中国中央電視台)は多くの中国漁船が日本に押し寄せると報道しましたが、他のさまざまな情報を組み合わせて真実ではないと分析できました。とくにヒューミント(人的諜報)の場合は故意に事実を歪曲する情報も含まれます。他のソースの情報と照らし合わせれば、真偽は多くの場合検証可能です。
――日本の場合はシギント(通信や電波を用いた諜報)の活用も重要でしょうが、いかがでしょうか。
北村:申し上げられない部分が殆どですが、ここでは同盟国との関係のなかで相当の役割を果たしているとだけ申し上げておきます。
――NSCやNSSの在り方について改善点を挙げるとすれば何でしょうか。
北村:いずれも事前に慎重な検討が重ねられて設置されただけあり、しっかりと機能していると評価しています。NSS設置前には、英国の国家安全保障担当首相補佐官だったキム・ダロック氏などからは会議で円滑な意志決定を行なうための秘訣などについて的確な示唆をいただきました。重要な案件を検討するうえでは首相、官房長官、外務大臣、防衛大臣が揃いますから、コンセンサスが得やすい。なぜならば、同じ情報だとしても各閣僚に別々に説明すると、報告者のニュアンスによって判断に差が生じかねませんが、その心配がないからです。
官邸について「裁断の場」という表現を用いましたが、安全保障の分野では、迅速かつ効率的にコンセンサスを形成することがとくに重要です。
――昨今、盛んに議論されているのが経済安全保障の重要性についてです。北村さんはNSS局長時代に経済安全保障に着目されましたが、どのようなきっかけがあったのでしょうか。
北村:アメリカ、我が国も含め先進国においては、電磁波やサイバー、そして宇宙を新たな戦域と見なしています。認識すべきは、いずれの戦域も技術に大きく依存している点です。私は、かつて警察で外事部門に長く勤務していました。最近の事件は、外為法や不正競争防止法が適応されるような先端技術の流出に係る事件が殆どです。ヤマハ発動機無人ヘリ不正輸出事件が起きたのは2007年ですが、それ以前から我が国の技術が流出していたわけで、私自身、どう対処すべきか問題意識を抱いていました。近年ではインタンジブル・テクノロジー・トランスファー(Intangible Technology Transfer)という言葉も用いられていますが、調査機関や大学などの研究機関における研究者等を通じた機微技術の流出も顕著です。
――経済安全保障に力を入れるには、インテリジェンスの側面においても従来とは異なる能力が必要になると考えるべきでしょうか。
北村:そう思います。たとえば、外国人投資家による対内直接投資案件について、どう扱うかを考えたときには、資金の流れ、投資主体、資金提供者、懸念国との関係等さまざまな対象についての情報収集が必要になります。これらの問題については、NSSの経済班が意識を浸透させる役割を担いますが、主管官庁を中心にインテリジェンス・コミュニティ全体を巻き込んで横断的に取り組むべき課題と言えます。
「政治主導」をどう考えるか
――安全保障にかぎらず幅広な意味での官邸主導や政治主導のメリットとデメリットについて考えたときに、近年ではとくに政治主導が強過ぎると官僚が萎縮するという議論があります。
北村:私自身、橋本龍太郎総理の時代に官房総務課企画官として中央省庁等改革を担当しました。当時は、官邸における意志決定の迅速化や機能強化は至上命題として語られていました。そして実際に、その方向で改革が進んできたわけです。戦後政治のなかで、行政制度がどのように変革されてきたかを理解せず、ただの印象論として「昔は良かった」と議論することが、果たして健全と言えるかどうか。内閣人事局が強くなり過ぎたというのであれば、まずは、いかなる理念に基づいてそれをどのように改革するのかという理屈が明示されるべきです。
そもそも政治とは、国民から選ばれた民主的正統性のある政治家が物事を裁断し、官僚はそのための準備をいかに整えるかに尽きます。もちろん、政治主導にも弊害がないわけではなく、行き過ぎかどうかを検証する必要はあります。しかし、いずれにせよ、政府機構全体の改革について、従前の流れをふまえて議論するべき話でしょう。
――内閣官房や内閣府が肥大化し過ぎているとの声もありますが、この点についてはどう考えますか。
北村:それも同じ議論で、極論すれば「肥大化すべきだ」という方向性でこれまで議論が進んできたわけです。安倍内閣の意向が働いたと指摘する向きもありますが、内閣の機能強化は橋本内閣以来の大きな潮流です。そうした歴史のうえで現在の国や政府のかたちが築かれていることは理解すべきです。また、民主国家である以上、いまさらそれは押し戻しようのないことでしょう。各省庁が群雄割拠していた時代には、セクショナリズムに起因する不祥事が頻発していたわけで、だからこそ国民から選ばれた内閣が実質的に裁断することができる制度に変わってきたわけですから。
日本周辺ほど軍事的緊張が高い地域はない
――最後に北村さんの国家観についても伺えればと思います。日本はいまインテリジェンスにかぎらず、さまざまな面でアメリカに依存していますが、この現状をどう認識されていますか。
北村:アメリカとの同盟関係は、我が国の戦後の国家戦略の柱です。そうした流れのなかで、インテリジェンスの分野においても一定の役割を果たしていかなければなりません。このひと言に尽きると思います。アメリカ依存を脱却すべきと語る方もいるようですが、そうした議論は現実を直視していません。時には日米中の三角関係という言葉が使われたこともありましたが、これも私には到底信じられない考えです。
――日本はこれからどのような国をめざしていくべきでしょうか。
北村:やはり現在の我が国の在り方をどう発展・改良するかという考え方に拠るべきではないでしょうか。もちろん、憲法改正の議論はありますが、日本国憲法には、議会制民主主義の基礎となる普遍的価値が定められているわけです。それに基づいて制度設計を行なっていくということだと思います。何ごとも歴史のなかの連続と非連続のなかで考えていくしかないのです。
――現在の日本をとりまく国際情勢のなかで、とくに注目されている点はありますか。
北村:世界を見渡したとき、極東ほど軍事的緊張感が高い地域はありません。たとえば年間のスクランブル発進の回数を比較すると、NATOの領空では500以下ですが、わが国の周辺は500から1,000の間です。この現実をまず認識しなければいけません。
それから尖閣諸島周辺海域には、中国海警船舶が毎日のように遊弋しています。海上保安庁と海上自衛隊はつねに中国の公船と対峙している状況にあるわけで、海と空の両方でこのような軍事的な緊張が存在しているのです。かかる現実は、国内では十分報道されていません。今秋は自民党総裁選や衆議院選で一色でしたが、我が国の安全と平和をいかに守るかは国民全体が認識すべきだと思います。
――台湾問題も予断を許しませんが、この点についてはどうご覧になりますか。
北村:習近平主席にとって台湾は核心的利益であり、妥協することはないでしょう。我が国にとって、台湾海峡の問題が地政学的かつ戦略的に重要なことは疑いようもありません。尖閣を含めた第一列島線上において、我が国の平和と安全をいかに守るかが大きな課題です。
――今日のお話を伺って、いかなる問題においても歴史的背景や連続性をふまえて議論することが重要であると再認識しました。いまの日本から失われている姿勢であり風土かもしれません。
北村:制度設計を行なううえでは、過去との連続性のなかからでしか判断できません。もちろん、歴史的に見れば不連続の局面がないわけではありません。たとえばGHQから占領中に示され、運用された旧警察法は、長く続きませんでした。これは現実を無視した理念先行の改革が社会に根付かないことを示しています。歴史的連続性のなかで現実的な解決策を見つけることが重要であるということなのでしょう。
※無断転載禁止