岐阜県・土岐「光洋陶器」

光洋陶器は「美濃焼」でも知られる土岐市に本社工場を構える
「モノづくりの国」岐阜
かつて織田信長が拠点と定め、中国に伝わる故事にならい命名された「岐阜」。長良川や木曽川がしられるように自然が豊かで、県内の各地がそれぞれの気候や地形にあわせて独自の文化や技術を発展させてきた。美濃地方の和紙や関市の刃物など全国的に人気がある産業が多く、いまも「モノづくり大国」としてしられている。
なかでもとくにシェア率が高いのが陶磁器である。岐阜といえば「美濃焼」の産地だが、県環境生活部統計課の資料によれば、和飲食器42.2%、洋飲食器68.4%と圧倒的な全国1位を誇る。美濃焼とは岐阜県東部・東濃地方の多治見市・土岐市・瑞浪市の3市で主に生産される陶磁器で、まさしく押しも押されもせぬ一大ブランドだ。
そんな岐阜県の土岐市に本社工場を置き、国内外の食のプロフェッショナルに向けた製品群の品質・デザインが定評を得ているのが光洋陶器である。3代目の加藤伸治・代表取締役社長は次のように語る。
「私たちは食器をつくるメーカーですが、この世界は幅広くて、安い値段で小売店に卸す会社もあれば、作家の方が一つ何十万円の作品をつくるケースもある。そのなかで当社は、国内外のホテルやレストランなど、プロフェッショナルの方に向けて製造しています。
プロの方に認められるものとなると、品質からサービスに至るまで高いレベルを求められるので、私たち自身がしっかりとした商品、さらにいえば『価値』を提供するプロでなければいけません。社員数は105名ほどですが、モノづくりからデザインや販売、広報など、それぞれの現場で働く社員がプロとして働いています」(加藤氏)
光洋陶器の創業は1964年、前回の東京五輪が開催された年だ。加藤さん曰く、「もともとこの地域(東濃地方)は海外に製品を輸出する会社が多かった」のだという。当時はまだ労働力が安く、しかも円安という追い風もあったので、「安くつくって海外で売る」というサイクルが回っていた。
しかし、1985年のプラザ合意で、風向きが大きく変わる。以降は多くの会社が、国内にマーケットを振り向けた。そうして、光洋陶器も現在のようにプロ向けの製品づくりに舵を切ったわけだが、それにしても平坦な道ではなかった。そんな苦難の時代にカギを握ったのが「質的価値」であったという。
泥臭くても「第3の道」を突き進む
光洋陶器が国内にマーケットを移した30年前は、業界全体が「量」を重視する時代だった。光洋陶器もインドネシアや中国に合弁会社をつくり、大量生産の体制を整えていた。しかし、その手法にも次第に限界がみえてくる。加藤社長が入社した18年前は、会社の方向性にふたたび変化が生まれていたタイミングだった。
「業界自体は、まだ大きい工場で大量にモノをつくるサイクルが主流でしたが、一方で、嗜好の多様化が進んできており、個々の細分化されたマーケットに向けて高価格帯の製品をつくる流れも顕著になってきていました」(加藤氏)
これは陶器にかぎった話ではない。たとえばアパレルでは、安いものはどんどん安くなり、その一方でハイブランドのものも人気だ。家具も一緒で、安く売る量販店に対して、中小のメーカーは高い商品を売らざるを得なくなる。しかしこうなると、消費者にとって手が届く価格で、なおかつ誰もが頷く品質や世界観も備えた商品は市場のなかで少なくなってしまう。
「だからこそ私たちは、その『第3の道』ともいうべき方向にこそ会社の未来の可能性があると考えました。昨今、お客さんのニーズや嗜好もさらに細かくなっていると感じています。たとえば、コーヒーのマーケットに特化したORIGAMIというブランドで、コーヒーカップやドリッパーをつくっていますが、それにしても好きな方は趣味としてどこまでも追求されています。当社がそうした方にリーチするには、サービスはもちろんのこと、ブランド力を磨かないといけません。最近ではとくにそう意識して、活動しているところです」(加藤氏)
量ではなく質の価値を追い求めて、それを消費者に提供する。興味深いのは、加藤社長は質的価値を届けるうえでは、テクノロジーの活用がカギになると考えているところだ。とりわけ伝統産業の「モノづくり」の世界では、手作業が重宝されがちではないだろうか――。そんな質問をぶつけてみた。
「生産性や効率、コストという観点から、自動化は避けられません。伝統産業や地場産業という領域では、どうしても『日本のモノづくり』というイメージが前面に押し出されすぎて、機械は敬遠される傾向があります。ですが当社では10年以上前から、多品種を少量生産するという生産体系のなかで、工場内も販売も自動化を推進してきました。それもすべては、手作業のよい部分を最大限に発揮するため。たとえばモノや情報を右から左に動かすだけの単純作業は機械に置き換えて、その分の時間、人にまさに質を追求する仕事に集中してもらうべきです。工場内の仕事でいえば、技術や改善を加えるなど付加価値を与える作業に関しては、結局のところは人でないとできませんから」(加藤氏)

光洋陶器代表取締役社長を務める加藤伸治氏
「モノからコトヘ」とは昔からよく語られるが、メーカーからすれば、モノをつくって売る仕組みから抜け出すことは容易ではない。「感性の部分も含まれるコト、つまりは質的価値をお客さんに届けることは人にしかできない部分がある」と加藤社長は語るが、だからといってすべて手作業では、多くの消費者に手の届かない商品の値段になってしまう。だからこそ、ある部分は機械に任せて、人間の負担を減らすことも必要なのだ。
ビジネスの世界にかぎらず、誰しもが「AとBのいずれを選ぶのか」という思考回路に陥った経験はあるだろう。このように物事を単純化したほうが、たしかに決断はしやすい。しかし加藤社長の話を聞けば、「大量生産か、高単価か」「手作業か、機械か」などという問題に対して、あくまでもその中間である「第3の道」に可能性を見出そうとしていることがわかる。
「繰り返すようですが、そこに私たちが生き残る道があると考えているからです。商品の付加価値を上げるとともに、いかに作業効率を上げてコストを落とすかというサイクルを回すことができなければ、企業としての存在価値はありません。規模の世界の話になれば日本は海外に太刀打ちできませんし、高単価の嗜好品をつくるのであれば、いまの時代はユニークで発信力をもつ個人の作家がたくさんいる。ならば、試行錯誤しながら泥臭く『第3の道』をつくる側に回らないといけません」(加藤氏)
そうして質的価値を生み出すことができれば、企業としての継続性も担保されるだろう。そして何よりも、消費者にとっても多様な商品と出合える可能性が増えるわけだから、まさしく好循環というわけだ。
ネットワークそのものに価値がある
本連載では、各地の青年会議所のリーダーに「質的価値」をどう捉えているか、質問をぶつけてきた。ひと言で簡単に回答できるテーマではないが、誰もが悩みながらも口を開き、自分の言葉を紡いでくれた。今回、光洋陶器の取り組みを受けて、公益社団法人日本青年会議所で2021年度岐阜ブロック協議会を務める柳憲嗣会長はどう感じただろうか。
「質的価値を紐解くには、さまざまなキーワードがあると思うんです。そのなかでもまずはやはり、何ごとも量で量る世界から脱却し、質の追求をめざすことでしょう。加藤社長の取り組みはまさに、質的価値の体現そのものだと感銘を受けました。もう一ついうならば、もともとその地域が備えている独自の力や魅力に、私たちのようなまちづくりの団体や、光洋陶器のような企業の力が加わることでストーリーを生み出す。それが、地域の内外から『共感』を得ることに繋がるはずです。そうしてよい循環が生まれることが、その地域の持続可能性にもつながっていくのではないでしょうか」(柳氏)
冒頭で紹介したように、東濃地方はもともと食器の生産量で全国のトップシェアを誇っている。その一翼を担う加藤社長は、地域との関係性をどう認識しているか。
「もともとは各社が分業体制をとって伸びた地域でもあるので、そのときにできあがったネットワークは現在も残っています。じつは世界的にみても、こうした地域は珍しい。ただし柳さんがおっしゃった『持続可能性』という点でいえば、いまは境目でしょう。業界でいえば生産量は最盛期の五分の一で、闇雲に量を求めていた時代から減るのはわかりますが、実際にサプライチェーンのなかで辞める企業や個人が増えています。このままでは、連綿と紡いできたネットワークが崩れてしまいます。世界的にみてもネットワークそのものには価値があり、もし一度壊れれば取り返しはつきません」(加藤氏)
そうした危機感は東濃地方内で共有されており、とくにここ1年、企業同士がどう持続可能なかたちで付き合い、生き残っていくかが話し合われているという。加藤社長も「可能なかぎり、光洋陶器のノウハウも地域に落としたいと思っていますし、同業であろうと工場内でみてもらえる場所は見学してもらっています。1社だけがこの地域で生き残れるものでもないですから」という。
このような地域のネットワークづくりは、日本各地で議論されている問題だろう。では、青年会議所のような組織はこの課題にいかなるアプローチが可能だろうか。
「青年会議所がいまやるべきは、自分たちだけで何か行動を起こすというよりは、自分たちが水面に落とした石のような『起点』となり、地域の課題を解決するスタンスだと考えています。そこで大事にしているのが『つなぐ』という意識です。SDGsの17個目も『パートナーシップで目標を達成しよう』という目標ですが、個々の力ではできないことも各種の団体や企業が集まって取り組めば、多くの課題は解決できる。青年会議所がその起点になるには、地域の方々のニーズを拾い、そのうえで声を上げることが大切だと考えています」(柳氏)
青年会議所が「つなぐ」役割を担うことに、加藤社長も期待を寄せる。8年ほど前にアメリカで工場を起ち上げる話が進んだとき、次のような経験をしたという。
「もともとは、アメリカのあるコーヒーチェーンが『アメリカで売るものはアメリカでつくりたい』と考えたところから進んだ話です。そこで陶磁器の生産が昔盛んだった地域に工場をつくり、私たちが機械やノウハウをもちこんで生産する計画でしたが、アメリカは早い時代に工場を海外に移してしまっていたので、その地域はすでにモノづくりの伝統が途絶えていました。
結果として工場稼働後数年で撤退する結果となりましたが、強く感じたのは、一度なくなったものを取り戻すことは非常に難しいということです。時代に合わせて変える姿勢は必要不可欠ですが、その先に続いていく仕組みをつくらないといけません。
ですが、企業側から地域を巻き込んで動こうとすると、どうしても1社でできることはかぎられています。東濃地方であれば、ユニークな企業はいくつもあって、まずは各自が自分の足で立つことが大切です。そのうえで互いに連携して、後世に残るネットワークや仕組みをつくる際、青年会議所あるいは行政に『つなぐ』役割をはたしてもらえれば、大きな可能性が生まれるでしょう」(加藤氏)
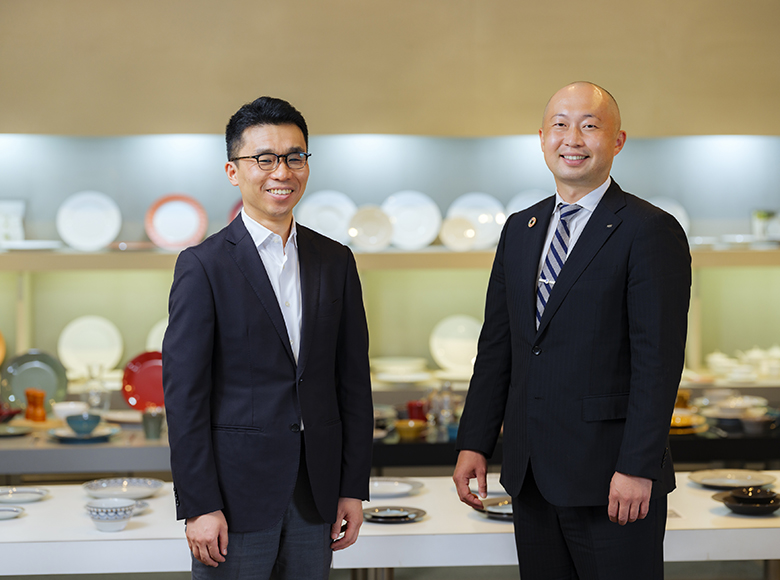
加藤氏(左)とJCI日本2021年度岐阜ブロック協議会会長を務める柳 憲嗣氏
「起点」としての青年会議所
柳会長曰く、岐阜は昔から自治意識が高い土地柄だという。「おすそ分け」の文化が残る地域もあるし、雪が積もったときには町内で集まって、互いの家の屋根の雪を下すのを手伝い合う。お祭り文化も根強く残り、人びとのあいだにつながりを生み出している。
「地域の連携は、まだ各所に残っています。そのなかで私たち青年会議所は、最初の旗振り役として多くの方を巻き込み、事業をつくりあげることが大事になる。私自身、岐阜ブロック協議会会長に就任して以降、多くの方へのヒアリングを行ないましたし、そこでみえてきた各課題に向き合い続けています。ただし、課題が完全に解決されるまで青年会議所がべったりと取り組む必要はないと思っているんです。繰り返すようですが、私たちは『起点』であり、多様な課題をみつけて、その解決への道筋ができたら、あとは他の方や団体に引き継いで別の課題に向き合う。その連続が地域の活性化、さらには自立へとつながるのではないでしょうか」(柳氏)
東濃地方では、すでに3市の壁を越えた「セラミックバレー」という大きな動きもある。各企業が危機意識を抱き、業界としてあらためて一つになって、持続可能な活動をめざそうと動き始めているところだ。その流れを加速させる意味でも、青年会議所のようなフレキシブルな組織が重要なピースになるのかもしれない。
* * *
岐阜の地域としての課題でいえば、働き手不足が大きなテーマに挙げられる。この点については柳会長から加藤社長に対して「光洋陶器はいかがですか?」と質問する場面もあった。「現在はうちの展開するブランドを知って、この会社で働きたいという方が来てくれています。ただし業界としては、モノづくりの現場で働きたいという人が減っているのは事実です」という加藤社長の答えに対して、「社会に発信している付加価値がしっかりしている企業は、概して社員集めにも苦労していない印象です。結局のところ、理念に対して共感を生み出せているかがポイントで、これは青年会議所の活動だって同じことです」と柳会長が頷く。
このような立場を超えた「対話」が、地域にネットワークだけではなく、「活力」や「うねり」を生み出す源泉になるのは間違いない。
※無断転載禁止
掲載号Voiceのご紹介
<2021年9月号総力特集「五輪後の本題」>
- 佐伯 啓思/「西洋近代」に未来は築けない
- 吉見 俊哉/東京が打破すべき成長主義の呪縛
- 高島 宗一郎/対症療法の政治から脱却を
- 原 丈人/日本国民の経済利益を守れ
- 清水 剛/「不確実性の時代」に生き残る企業
- 山本 昭宏/速度の現代民主主義と「怒り」
- ヨラム・ハゾニー/日本はリベラリズムと闘うべきだ
- 鈴木 康裕/日本は台湾を死守せよ
<2021年9月号特別企画「『新しい戦争』に備えよ」>
- ルイス・A・デルモン/「超絶知能」は人類を排除するか
- 安田 淳/「戦わずして勝つ」中国の知能化戦略
- 小泉 悠/ロシアが目論む「新型戦争」
- 山田 敏弘/爆撃を超えるサイバー攻撃の破壊力
<ご購入はこちらから>

目次はこちら
View more

