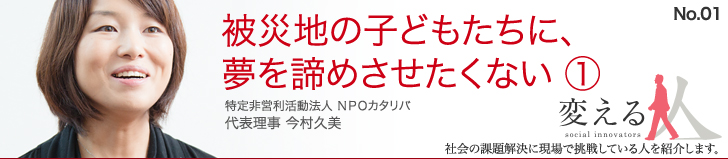家や学校を失った子どもたちに勉強の場を

NPOカタリバ 代表理事 今村久美
新連載「変える人」は、社会にあふれる課題を解決すべく「現場で」活動を展開している方々を取材し、ご紹介するインタビューコーナーです。
第1回は、東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県女川町・岩手県大槌町で放課後学習塾「コラボ・スクール」を運営する、NPO法人カタリバの今村久美さんをご紹介します。
********************
東日本大震災の巨大津波によって甚大な被害を受けた東北地方沿岸。宮城県女川町と岩手県大槌町では、中心市街地が壊滅してしまった。
「震災があったから、進学や夢を諦めた」。
そう思ってもやむ得ないほどの、あまりの被害だった。家や学校は流され、勉強する機会は失われた。でも、こんな大変なときだからこそ、子どもたちには意欲をもって前に進んで欲しい。落ち着いて学べる場を、何とかしてつくり出したい。そんな願いから始まった放課後学校がある。それが、「コラボ・スクール」だ。
「もの」は余っている。足りないのは「人」
「コラボ・スクール」を立ち上げたのは、今村久美さんが代表を務めるNPO法人カタリバ。もともとは首都圏を中心に、主に高校生向けのキャリア学習プログラムを提供している団体だ。被災地支援を手掛けた経験はなく、岐阜県出身の今村さんにとって、東北と特別の繋がりがあったわけでもない。
「震災の直後、私の指示ではないのですが、カタリバのボランティアメンバーが街頭募金を始めたんです。震災でいろんなものを失った子ども達に回るお金を、長期的な目線で集めなければいけない、と。2001年にカタリバを始めてから寄付を集めたことは一度もありませんでした。でも、このときは4時間街頭に立つだけで200万円集まるというような、今から考えても特殊な状況でした。最初は、自分たちで支援活動を直接するつもりはなくて、街頭でいただいた寄付金をうまく活用してもらえるパートナーを探すために東北へ行ったんです」
テレビやインターネットでは衣食住に支援が集中していたので、カタリバは自分たちの活動に沿って「子どもに関する支援」を打ち出して募金活動を行い、支援先を探した。そして4月17日に石巻に向かった今村さんは、東京で報道を見て抱いていた感覚と、現地の状況がまったく違うことに気がつく。
「イオンがすでに営業していたんです。ほかにも現地で商売をされている方がいて、遠くから食糧を買い込んで持って行かなくても、そこで調達できていました。5月には石巻の駅前で、うどん屋さんも営業を再開していました。なのに、そこから100mも離れていない公園ではずっと炊き出しが行われていたりして。これはどこかでひずみが起きるな、って思いました」
さらに、子どもに関する支援先を探す中で、被災地の子どもたちの学習環境がまったく整っていない現実を目の当たりにする。
「避難所は夜9時には電気が消えてしまって、子どもたちは夜勉強する場所がなかったんです。学校の先生たちは、自らも被災しているにもかかわらず何とかしようと頑張っていたけれど、働き過ぎで県から勧告が出るほどで。ボランティアによる無料学習塾もあったけれど、こちらは思うように子どもたちが集らない、といったような状態で」
教えたい意欲も、学びたい意欲もあるのに、マッチングができていない。このままでは、子どもたちの学習環境の問題は後回しになってしまうだろうと思われた。この問題に正面から取り組んでくれそうなパートナーも、当時は見つけられなかった。
「2週間くらい現地に滞在して感じたのは、“人が足りない”ということ。必要な資金は集まってくる。ものも集まってくる。鉛筆や問題集やノートなんて、『もう置く場所がありません』っていうくらい、避難所に大量に積み上げられているんです。だけど、腹をくくって支援に取り組む“人”が見当たらない。支援したい人と現地のニーズを、ニュートラルな立場でつなぐ機能が欠けていることを痛感しました。だったら、自分たちがその立場にならなくてはいけないって。ほとんど衝動的だったんですけど」
このとき、組織の中で意思決定をしていたわけではない。だが、代表である今村さんが走り出すと、カタリバのメンバーも信じてついてきてくれたという。しかし、活動開始の手掛かりさえ、つかむのは容易ではなかった。

校庭に仮設住宅が建つ被災地の小学校
やると決めれば、事態は動く
「最初は石巻でやろうと思っていました。でも、例えばタウンページも津波に流されてしまっていて、とにかく現地には手掛かりがなにひとつありませんでした。どうにか石巻駅の近くでインターネットが使えるところを見つけて、『石巻学習塾』とか『石巻教育委員会』とか、教育関係だと思われるところに片っ端から連絡していきました」
石巻教育委員会と連絡を取り合い、何度も東京から石巻を訪れては打合せを重ねた。しかし、ここで行政の壁にぶつかる。公平性を重要視して、市内全域での取り組みが必要だとする市。内容云々ではなく、かたちの調整に時間が割かれるばかりだった。
「できるところから始めればいいじゃないですか。公平性も大事だけど、一箇所でもいいから、モデルをつくっていきましょうよ」
そんな今村さんの訴えも、なかなか通じない。だが、行政が公平性にこだわったのにも、理由があった。当時、平成の大合併で大きくなった石巻市では、旧河北町に位置する大川小学校の悲劇がメディアで繰り返し報道されていた。一方で、旧石巻市の中心部に関心や支援が集中し、被害の甚大だった旧町の住民との間には亀裂が生じていた。そうした住民感情に配慮し、行政も支援の偏りには慎重にならざるを得なかったのだ。今村さんは別の自治体にも並行してアプローチすることにし、石巻市に隣接する女川町の教育長のもとを訪ねた。
「私たちの思いを伝えたら、教育長さんがその場で『やりましょう』と。やっぱり、リーダーがやろうって言ってくれたら、ものごとは動くんです。石巻市全域でいっぺんに学習支援に取り組むのはむずかしいから、いったん女川にリソースを集中してモデルをつくろう。それからほかの自治体に広げよう。そう決めて、とにかく女川に通いつめました」
女川町の避難所に泊まり込み、教育委員会や住民の方々とコミュニケーションをとる日々が、ここから始まった。だが、教育委員会や学校との連携が第一と調整に努めたものの、外部との連携に二の足を踏む教員も少なくなかった。また、地元で開講していた学習塾が被災した塾講師を雇用したものの、それぞれに指導スタイルが異なるなど、悩みはつきなかったという。
「保護者の方々や生徒の皆さんにいろんな話をうかがったら、確実にニーズはあるという確信を得た一方で、信頼関係のできていないところには子どもを預けられないということも感じました。遠方から通ってのボランティアだと、交通費ばかりかかって、せっかくの寄付もそれで消えてしまう。住民の方たちを雇用して仲間になっていただこう、住民の方や行政の方と交流して信頼関係をつくっていこう、そのためには現地に住んで取り組む体制をとらなきゃだめだ、と強く思いました」
こうした努力が実り、2011年7月4日、初めての放課後学校「コラボ・スクール」となる女川向学館が開校する。教育長の承諾を得たのが5月15日だから、驚くようなスピードだ。
「このとき、実は資金計画はまったく立っていませんでした。文部科学省の予算をもらえることになったのは11月でしたし。だけど直感的に、これなら大丈夫と思いました。被災地への支援に対する世の中の熱い思いを肌で感じていて、女川で学習支援をやりますってお願いすれば必要な資金は集まるはずだ、と思ったんです。そして実際に集まりました。旗を揚げればリソースは集まる。いないのは旗を揚げる人。それは2年半経ったいまでも同じなのではないでしょうか」

コラボ・スクール「 大槌臨学舎」に掲げられた看板
子どもたちの未来のために、 できることはすべてしたい
女川向学館開校に遅れること5カ月、コラボ・スクール2校目となる大槌臨学舎が開校する。高校受験3カ月前という時期もあり、最初は中学3年生だけに特化して学習支援を行った。スタッフも子どもたちも、とにかく必死だったという。いまでも大槌臨学舎に通う高校2年生の吉田くんは、当時をこう振り返る。
「震災があったのは、中学3年生に進級する直前で。自分の家も被災して仮設住宅に移ったんですけど、やっぱり狭いし、周りのテレビの音も聞こえてくるし、ぜんぜん勉強に集中できなかった。そんなところにコラボ・スクールができて、友達と一緒に勉強できるし、わかりやすく教えてくれるし、受験のときは本当に助けてもらいました」
大槌町にはもともと学習塾がほとんどなく、塾に通った経験のない子どもや親が大半を占めていた。コラボ・スクール設立に際して町の協力でアンケートをとってみたところ、通塾率は10%を切っていた。教育委員会にも、「この町で、そんなもの開いても、来る子なんていないよ」と言われたという。それでも教育委員会の理解を得て公認をもらい、学校で告知されるところまでこぎ着けた。無料で生徒を募ってみれば、学びの場を求めてコラボ・スクールに通う生徒は100人にのぼった。
「震災がきっかけだったのか、それ以前からだったのか。保護者の方たちのお話を聞いていると、子どもの未来のためにできることはすべてしたい、という思いを強く感じました。だから、これまで塾に通ったことがない子どもたちまで、コラボ・スクールに来てくれたんだと思います。いまでは教育委員会とも、いい関係を築けています。立ち上げのときは、教育委員会や役場って、なんでこんなにたらい回しなんだろうって思ったこともありました。けれど、震災直後は、いろんな人たちがNPOという肩書きで、それこそ大量に被災地にやってきていました。町の方でも、誰を信じていいのかわからなかったんだろうと、いま振り返ってみると思います」
いざ開設、といっても場所選びには苦労した。今年10月に新校舎がオープンするまでは、町の公民館を借りて授業。どうにか津波に耐えた施設で、倒壊こそしなかったものの浸水被害を受けていた。そんな場所に子どもを通わせることはできないという保護者や、すぐ近くで震災に遭ったトラウマからその辺りに近づきたくないという子どもたち。ほかに間借りできる場所がない中での、やむを得ないスタートだった。
スタッフの住む場所を見つけるのも大変だった。仮設住宅は被災した住民の仮の住まい。とくに大槌町では町内の仮設住宅に入れない住民もいたため、とても入らせて欲しいといえる状況にはなかった。いまでこそ、一人一部屋を確保したシェアハウスに落ち着いているが、最初の1年ほどは、プライベート空間などとてももてなかったという。
「和室に布団を敷き詰めて寝るんです。自分のスペースって言えるのは布団の上だけ。一番多いときには15人で一軒家に住んでいました。だけど、滞在できる場所が見つかっただけでも、運がよかったと思います」

休み時間に生徒と談笑するスタッフ
悲しみを強さに変えて
そんな立ち上がりの困難を乗り越え、大槌臨学舎が開設してから約2年。子どもたちには、これまでと違う変化が見られるという。被災者として、支援される側にいて、いい子でいることに疲れてしまった面があるのかもしれない。なかなか進まぬ復興と、いつまで続くのかわからない仮設住宅での暮らしに、張り詰めた気持ちが切れることがあったのかもしれない。
「震災直後から疲れたと言ってる子もいるし、ほんとうにそれぞれのタイミングなんですけど、疲れたと表に出して言う子が増えているのを実感します。それが震災の影響なのか、それとも思春期の難しさなのか、容易に判断のつかないところでもありますが。がんばれって励ます部分と、がんばらなくていいよと労わる部分と、使い分けが本当に難しい。もちろん、全員が疲れているわけじゃなくて、やる気に満ちあふれている子もいるし、逆になにかやっていないと辛くなるという子もいる。勉強をがんばったことで、心が復活したという子がいるのも事実です」
今村さんをはじめ、コラボ・スクールのスタッフが心を砕いているのは、「なにができるようになったのかを、目に見えて感じさせるプログラムを組むこと」だ。人に支えられ助けられながら課題に向き合い、以前できなかったことができるようになったと実感することは、心のケアにつながる。それは同時に、「震災を理由に、子どもたちに夢を諦めてほしくない」「震災の経験を、悲しみから強さに変えて、社会のリーダーになれる人材に育ってほしい」という、今村さんの願いにも重なる。
子どもたちが自ら主体的に将来を考え、チャレンジによってものごとは変えていけるという次の目標に向かって、コラボ・スクールでは新たな取り組みが始められていた。 (第2回「子どもたちの未来に、たくさんの選択肢を」へ続く)
【今村久美 略歴】
いまむら くみ*1979年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。大学在学中に2001年に任意団体NPOカタリバを設立し、高校生のためのキャリア学習プログラム「カタリ場」を開始。2006年には法人格を取得し、全国約400の高校、約90,000人の高校生に「カタリ場」を提供してきた。2011年度は東日本大震災を受け、被災地域の放課後学校「コラボ・スクール」を発案。
【取材・構成:熊谷 哲(PHP総研)】
【写真:shu tokonami】