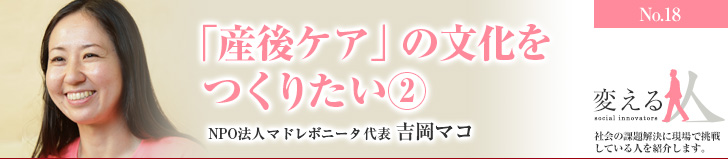産後ケアの普及による社会問題の予防と解決を目指して

吉岡さんのインタビュー第1回はこちら:「産後の女性を支える社会的インフラを」
パートナーとの離別と教室の休止
産後ケアエクササイズの教室を開く。そう決めてからの吉岡さんの行動は早かった。絶対にニーズがあるはずだという確信を持って場所を探し、チラシを作成した。
「チラシをつくったのは、出産から3か月ほど経った6月頃。9月スタートということにして、集客を始めました。当時はメールもまだ普及していなかったので、お世話になった助産師さんにお手紙を書いて、『関心のありそうな方がいらっしゃったら教えてください』とお願いしたりして」
助産師の方も「出産で傷ついた会陰の手当はしてあげられるが、産後の肩こりや腰痛の悩みをケアしてあげられない」と困っていたといい、産後の母親がリフレッシュできるような場があるのならぜひ行ってもらいたい、と積極的に紹介してくれた。
「そうやって申し込んでくださった方がお友達を連れて来てくださったりして、最初の教室は7人でスタートしましたが、翌月早速集客の壁にぶつかりました。9月の教室はほぼ満席でしたが、10月、11月はかなり空きがあって」
多くのビジネスでは、リピーター率を上げることが安定した収益につながるが、産後ケアという性質上、基本的には毎月新規顧客を獲得しなければならない。これは現在でも一番の課題だ。
「新聞に取り上げていただいたおかげで12月にはまた満席になったんですが、新聞の効果もそう長くは続かない。毎月集客しながらやっていくのは難しいな、と思って、実は一回教室を止めました。ちゃんと働かないと、この教室だけではやっていけないな、と思って」
実はこの頃、吉岡さんはパートナーとの離別を迎えていた。パートナーは外国で行われる研修会に参加したときに知り合った現地の男性だったが、吉岡さんは出産のために日本に戻り、二人は離れ離れに。出産前後の不安定な時期を遠く離れて過ごしたことは、その後のパートナーシップにも大きな影を落としていた。
「出産するまでは私もその国に戻って一緒に暮らそうと思っていたのですが、出産後のぼろぼろな感じを味わってしまって、こんな状態で家を引き払って子どもを連れて外国に行って暮らすなんてことは考えられなくなってしまって。子どもが8か月になる頃、『もう一緒にはやっていけない』ということを伝えて、日本で一人で子どもを育てることにしました」
パートナーがいなければ、家事ばかりでなく、金銭面でも生活の面倒をすべて自分で見なければならない。安定した収入が必要だった。とは言え、新卒一括採用も終わっている時期。就職口を探すのも簡単ではなかった。
「大学院中退で、乳飲み子がいるので17時に帰りたい、という条件では正社員で雇ってくれるところはなくて、結局、翌1月からある出版社に契約社員として入れていただきました。月曜から金曜まで、毎日9時から17時半まで働くと、土日に何か別のことをするというのは体力的に無理で、教室は諦めるしかありませんでした」
しかし、その間にも新聞記事を見た人からの問い合わせは途切れなかった。勤務を終えて家に戻ると、教室への参加を希望する手紙やFAX、留守電へのメッセージが届いていた。
「ご連絡をいただいた方には、いまはお休みしていることを伝え、再開するとしたらご案内していいかお伺いして、参加希望者リストをつくっていました。そうしながら、参加したい人はいるんだけど、需要と供給が一致しない。集客が安定しないとやっていけないけれど、希望者は確実にいる。というところにジレンマを感じていました」