安全保障とデジタルを連結せよ
米中が覇権を争う時代に菅政権はいかに立ち向かうのか。第二次安倍政権で共に国家安全保障局次長を務めた防衛と外交のスペシャリストが、あるべき経済安全保障政策から菅総理のリーダーシップまで語り尽くす
NSCで政治と軍の〝神経〟が繋がった
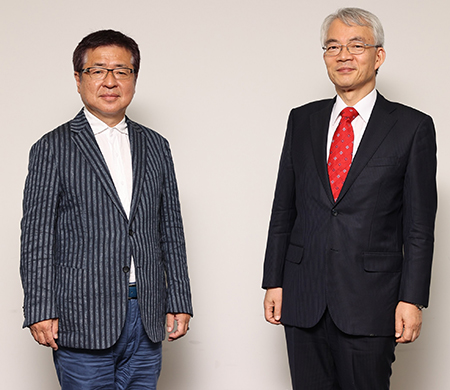
――(金子)お二人とも第二次安倍政権で、NSC(国家安全保障会議)の事務局組織であるNSS(国家安全保障局)の次長を務めた経歴をおもちです。2013年に創設されたNSCには、どのような意義があるとお考えですか。
高見澤:同組織を創設したことにより、我が国の外交・安全保障政策における意思決定過程では五つの点で大きく変わりました。私はまずこの事実を正しく評価すべきだと考えています。
それぞれ挙げていくと、一つは、政府から各省庁の職員に対して政策の明確な情報要求が行なわれるようになり、情報の流通や共有が進みました。この情報共有が国際社会を生き抜いていくカギだという意識が徹底しました。二つ目は、国家安全保障局長も含む職位上位者から下まで調整や共同作業を行なう、いわばワーキングレベルでのチームができたこと。三つ目は、政策の意思決定がスピードアップし、スタッフも充実したことにより、危機事態への継続的な対処と中長期的な政策目標の練り上げを、並行して実施することが可能になりました。四つ目は、会議の議長である総理のリーダーシップが徹底され、サイバーや宇宙など新しい領域も含め省庁間の垣根を越える横串ができたこと。五つ目は、各国のNSC、とくに同盟国アメリカとの間でカウンターパート同士の新たなチャンネルができたことです。
兼原:私は、NSCによって政治と軍(自衛隊)の〝神経〟が繋がった点を強調したい。とくに政治の側が予算案の決定だけではなく、自衛隊がどう使われるかという作戦運用面にまで問題意識をもつようになったことは大きな変化です。もともと政軍関係の改革の必要性を認識していた安倍晋三前総理や麻生太郎副総理がいたからこそ、NSCの創設に至りました。
省庁間調整に関しては、外務省、防衛省、警察庁がそれぞれ担っている役割が横で繋がりました。諸外国では、ディプロマシー(外交)、ミリタリー(軍事)、インテリジェンス(諜報)という安全保障に関する三本の神経が政府上層部で統合され、連結されているのが常識です。バラバラだった三つのラインが、総理が主宰されるNSCと、総理を補佐するNSSの両方のレベルで結び付いた点は大変意義深い。
高見澤さんが最後に挙げた日米関係では、従来の大きな問題点は、ホワイトハウスのカウンターパートが明確でなかったことです。日本側は外務省がその役割を担うと認識していましたが、ホワイトハウスからすれば外務省は国務省のカウンターパートにすぎない。2013年のNSC発足以降は、ホワイトハウスと日本側のNSC、ペンタゴン(国防総省)と防衛省、国務省と外務省がそれぞれ対応した上で、調整し合うかたちが確立されました。
省庁間の連携のスピードも、間違いなく上がりましたね。私が所属していた外務省サイドからいえば、防衛省の内局に情報の提供を要望すると、それが伝言ゲームのように三幕(陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部)へと降りていき、依頼してから返事が来るまでに一週間を要することもあった。これでは緊急事態に対応できるはずがない。NSCが発足してからは、そのスピードがだいぶ上がりました。
印象に残っているのは、2014年3月にマレーシア航空370便が突然、消息を絶ったときのことです。マレーシア政府から捜索の支援要請を受けたため、NSCの朝会でこの件を諮りました。すると同日午後には統合幕僚長が総理の指示を得て、航空自衛隊、海上自衛隊の航空機派遣が決まった。航空機事故の救難要請に対して自衛隊機を派遣したのは初めてですが、これまでにないスピードで決定が下りました。
高見澤:安全保障戦略でいえば、国際情勢の変化、とくに脅威が増す中国に対しての認識を日本政府のなかで共有できたことも画期的でした。その後、これを基に同盟国である米国や関係国とも幅広い議論ができたことが、現在の対中政策の礎になっています。とりわけNSCが発足したことで、中国の世界各地における動向、国防費の急増や軍備拡張の実態、拡大するオペレーションの状況について総合的な分析と検証を行ない、省庁横断的に議論できたことはよく覚えています。
兼原:当時は、中国の軍事費が急増していても、いまほど問題にされなかった。そこから対中政策の議論が本格的に始まり、「日米同盟をさらに強化しなければバランスがとれない」という危機感が急速に広がっていきました。さらに、「国防の基本方針」に代わるものとして2013年に作られた「国家安全保障戦略」で、豪州やインドの重要性が強調されました。それが、クワッド(日米豪印戦略対話)の進展や現在の「自由で開かれたインド太平洋」構想に繋がったことも、NSCの存在なくしては語れない成果でしょう。
国策をいかに統合的に運用するか
――NSCで安全保障の実務を担ったなかで、とくに難しかった出来事は何でしょう。
兼原:2014年2~3月に起きたロシアのクリミア併合は印象深いです。当時、外務省は米国との関係を重視してロシアに対する制裁発動を推す一方、安倍総理はもちろん日米関係の重要性を認識しながらも、同時に日露関係の修復にも尽力されていた。その難しい局面において、外務省と総理の結節点となって調整を行なったのがNSCでした。じつは欧州諸国も足並みが揃っておらず、ロシアへの制裁を主張する国もあれば、エネルギーを同国に依存している事情から静観する国もあった。多様な利害が絡み合う重要懸案をすり合わせる作業では、内政、外政の微妙なバランスが重要です。まさしくNSCのような組織の出番でもあります。
高見澤:私は、危機対応という観点から申し上げますが、日本の場合、巨大地震や大型台風といった自然災害を相手にすることが多い。我が国は国際的な事案への対応と並行して、災害対応のウェートがほかの国よりはるかに重いというのが実感です。
在籍当時を振り返れば、いわゆるグレイゾーンと言われる分野において、警察と海上保安庁、そして自衛隊(防衛省)という三つの組織の大方針の統一を図ることは容易ではありませんでした。幸い、NSCの設置もあり、実際の現場での協力関係の進展と制度的問題への取組みの進展により、大いに改善されてきたとはいえ、各組織の役割の棲み分け、壁が伝統として残っている感は否めない。今回の新型コロナ禍への対応もそうですが、未知の脅威による〝有事〟が突発的に起きた際、ほとんどの省庁が関係してくる国策をいかに統合的に運用するかについて、依然として改善すべき点があります。
経済と安全保障は一体で考えるべき
――2020年4月にはNSSに「経済班」が新設されました。米中のハイテク覇権争いの先鋭化にみられるように、経済と安全保障は密接に関わっています。経済班新設の狙いや意義をどうご覧になりますか。
兼原:3年ほど前、経済産業審議官(当時)の柳瀬唯夫さんが「兼原さん、何やらアメリカの様子がおかしい」と、私がいる補室(内閣官房副長官補室)に飛び込んできました。旧友の柳瀬さんは国家全体を見渡す産業ヴィジョンをもった稀有な方で、米中技術摩擦にいち早く勘づいていた。当時はNSSのなかに経済官庁の幹部がいなかったので、補室に持ち込んできたのでしょう。
経済官庁の人たちは、先端技術がどのように軍事転用されるのか、じつは実態をよく知らない。たとえば、宇宙空間、サイバー空間が戦闘に利用されることが当然となっている現在、アメリカは宇宙のセンサーから情報を得て、情報を統合分析して処理する技術が他国に窃取されることを懸念しています。人工知能や先進コンピューティングだけではなく、優れた画像センサーに関する技術の流出にも敏感です。
補室では、外務、防衛だけではなく、さまざまな経済関係官庁を巻き込んで、外為法に基づく機微技術流出防止はもとより、防衛技術の育成上の問題や、領海内科学調査に関する問題など、さまざまな分野で一定の進展を見ました。それらは、皆、新設のNSS経済班で責任をもって引き継がれることになりました。いま経済班では、これ以外にも、溜まりに溜まった宿題を一度に下ろされて多忙を極めています。
高見澤:NSCが発足したのは2013年末ですが、その当時、アメリカの対中脅威認識は日本よりも弱かった。米中間で経済面での競争はするけれど、技術面で覇権を争うとまでは見られていませんでした。我々日本側としても、現在のような米中対立を前提とした議論をしていたわけではなく、その事実は率直に認めるべきでしょう。少なくとも、2013年12月に閣議決定した国家安全保障戦略のなかには、「技術覇権」という言葉は入っていませんでしたから。
NSCのアジェンダに経済的側面を入れるかどうかは、発足当初から議論はされていました。しかし見送られてきたのは、経済まで加えると安保戦略の焦点が薄くなってしまうとの懸念があったからです。先ほど申し上げたように、自衛隊と警察と海上保安庁は伝統的に役割が棲み分けられていましたが、それでも各々のカルチャーは似ていたから連携できた。翻って経済官庁と防衛省、外務省は文化がまったく異なり、共通基盤もなかった。しかし米中のハイテク覇権争いが加速したことを受けて、経済安全保障を想定した経済班の新設に至ったのだと思います。
NSSの経済班は、日本の国力回復において大きな役割を果たすはずです。我が国では昨今、遅まきながらDX(デジタルトランスフォーメーション)が進められています。「判子をなくす」といった効率性のレベルの話だけでは不十分という認識は広がりつつありますが、安全保障や技術戦略的な観点を加えて、サイバーセキュリティ能力の徹底的な強化策まで盛り込むことが必要でしょう。
兼原:高見澤さんが指摘されたように、NSSを担うミリタリーとディプロマシーとインテリジェンスの各部署には、国家の安全という共通の問題意識があります。しかし経済官庁には、国家安全保障という感覚はさほどない。もちろん、一概には言えないのですが、彼らはあくまでも経済を活性化させてビジネスを後押しする論理で動いています。
しかし、宇宙やサイバーの分野も視野に入れて、現代の戦闘様相を理解しないと、なぜアメリカが中国に対してあれほど危機感を募らせているのかわかりません。「現代の戦争」がどういうものか、先端技術が軍事にどう使われているのかを熟知するのはNSSと防衛省、自衛隊です。NSSを通じて安全保障関係官庁が経済官庁と連携することで、経済と安全保障がようやく繋がったのです。経済安全保障全般を所管する部署の設置は、戦後、初めてと言っていい。
高見澤:2010年9月、わが国固有の領土である尖閣諸島沖で中国漁船が日本の海上保安庁の巡視艇に衝突する事件が起きた際、中国は日本に対してレアアースの輸出を停止してきましたね。そのとき私は、対応を考える研究会で経済官庁の幹部OBに「日本が中国に何を依存し、何を強みとしているかを洗い出す良い機会じゃないですか」と言いました。ところが返ってきた答えは、「その発想が危険なんですよ」。残念ながら、こちらの意図がほとんど理解されなかったことをいまでもはっきりと覚えています。おそらく世代差もあると思いますが、当時は経済官庁で幹部にまでのぼりつめた方でさえ、経済と安保の関わりについてピンときていない状況ではなかったかと思います。
兼原:遺憾なことですが、そうした現状は日本が敗戦国であることも関係していると思います。戦勝国のアメリカやソ連(ロシア)は、国際的な秩序をどうつくるか、世界の安全保障をどう担うか、といった大戦略を描いてきました。もちろんその過程で、軍事と経済が一体であることを十分に認識して考えてきた。欧州連合が、石炭、鉄鋼、原子力のような分野で、ドイツの戦争遂行能力を国際化したのはその良い例です。
一方で敗戦国の日本は、冷戦開始前はもとより、冷戦中でさえ、米国に再軍備を厳しくコントロールされてきました。同時に、日本は米国に安全保障を依存していた。経済官庁は、安全保障には目をくれず、高度経済成長に邁進しました。そのため、経産省の安全保障貿易管理部門を除いて、軍事、安全保障のリテラシーが著しく低い。それは、官界だけではなく、一部重工業を除く経済界一般にも言えることです。最近は経済官庁の認識がようやく変わってきて、以前よりは経済安全保障への理解が深まっているようにみえます。
菅政権は「実行・実現内閣」
――安倍政権は「地球儀を俯瞰する外交」「国際協調に基づく積極的平和主義」「自由で開かれたインド太平洋」構想など、大局的な方向性を示して外交・安全保障政策を展開してきました。9月に発足した菅政権はどのような大戦略を描くべきでしょうか。
兼原:安倍政権では、政権内で役割分担がなされていました。外交安保は安倍総理の直轄地帯、内政は菅義偉官房長官、金融財政は麻生副総理という具合です。とはいえ、当時の菅官房長官が外交安保を疎かにしていたわけではありません。平和安全法制の制定には大いに尽力されましたし、すべてのNSC会合に同席されています。菅官房長官が総理になられたわけですから、これからは菅総理自身が外交安保のハンドルを握られるでしょう。民主主義や人権の尊重を標榜した安倍政権の「価値観外交」を継承しながら、菅政権としての新しいカラーが徐々に出てくるのではないでしょうか。
高見澤:そもそも官房長官というポジションは、安全保障に関する政策を検討する際、多様なソースから情報を収集し、全体の動きをみて、その実現可能性や段取りを考える立場にありますからね。政策の具体化に障害がある場合には、各省や与党と調整しなくてはならない。たしかに自ら戦略を構想する立場ではないかもしれませんが、少なくとも安倍政権下で、菅官房長官は平和安全法制など安全保障政策を実際に前に進めるという意味では深く関わってきたと考えています。
加えて、厳しい国際環境のなかでこれからの日本の課題は国力や生産性の向上です。菅政権が力を入れているDXや規制改革に関しても、サイバーセキュリティの強化や新技術への対応など安全保障の側面も含めて体系的に検討することにより、新しい戦略を展開できるのではと期待しています。
兼原:私個人の考えではありますが、菅官房長官は歴代の官房長官のなかでも出色な人物だと感じていました。過去の名官房長官といえば、元役人の後藤田正晴さんを除くとして、党人では霞が関を組み敷いた梶山静六さんが挙げられますね。野中広務さんもパワフルな方でした。菅官房長官が、梶山、野中両長官に増してすごいと思うのは、自民、公明の両与党との調整を図りながら、霞が関(官界)に対して官邸の指導力を大きく強めた点です。昭和前期以来、政権中枢の空洞化と権力の拡散が日本政治の課題でした。菅官房長官が、総理官邸のリーダーシップを高め、関係省庁を取り仕切ってさまざまな政策を実現してきたのは紛れもない事実です。
高見澤:その意味で、菅政権は「実行・実現内閣」になると私はみています。戦後日本を振り返ると、政権にアジェンダがあっても、具体化して実現させる「How」の部分が不足していることが多かった。安倍政権は安全保障政策の枠組みの設定という点で成果を上げましたが、菅総理は官房長官としてその実現に関わってきました。しかし、各省のなかでやるべきことはわかってはいてもなかなか実現できていないことがあり、国際的な公約でも、いまだに「国内制度の枠組みを超える」という理由からできていないこともある。これを打ち破らなければならないというのが、菅総理の問題意識ではないでしょうか。
中国がピークアウトするまで西側諸国で連携を
兼原:外交の大局的な観点から言うと、我が国は世界のなかで〝横綱〟ではないかもしれないけれども、〝大関〟の位置にはとどまっています。私はかねてより、日本は胸を張って世界で自由主義の価値観を掲げた外交を行ない、アジアのリーダーをめざすべきと主張してきました。安倍前総理が7年8カ月にもわたって推進してきた方向性でもあります。
中国は、二桁成長の時期を抜けて中成長期に入りましたが、当分の間は、経済的にも軍事的にもさらに伸びていくでしょう。しかし、これから20年ほどする間には、米国に追いつくかどうかというところで、おそらくはピークアウトします。現在、世界全体に占める各国のGDP(国内総生産)の割合は、米国が24.6%、中国が16.9%、日本が6%です(IMF、2020年)。インドは3.5%ですが、これから急速に成長していくでしょう。
中国の世界全体に占める経済力は大きくなっているとはいえ、世界の半分にまで達することはないと思います。最終的にはアジアのリージョナルヘゲモニー(地域覇権)で頭打ちする。同国による世界覇権の時代は来ない。したがって、自由主義の価値観を共有する西側諸国全体で中国と向き合っていけば、戦略的な安定を実現することは可能です。ただし当然、気を抜くことなく中国の膨張主義を注視し、こちらも努力しなければならない。同国がピークアウトするまで西側の団結と連携によって耐え忍ぶ。それが今後20年の日本の大戦略です。力関係の安定の上にのみ信頼はあります。関与も可能です。関与は懇願ではありません。
また、高見澤さんがお話しされたように、菅総理にはデジタル化の推進を謳うのならば、行政改革にとどまらず、サイバーインテリジェンスに繋げていただきたい。実現できれば、「安全保障とデジタルの連結」が菅政権の大きなレガシーになるはずです。
高見澤:兼原さんの指摘されたアジアのリーダーという点では、2005年に当時の麻生外相が打ち出した「実践的先駆者」たるべく努力するという構想もありました。また「課題先進国」という言葉が広がりましたが、日本として求められることは災害や感染症、サイバー攻撃といったあらゆる危機に強くなり、レジリエンス(復元力)をもち、なおかつ生産性を向上することですね。私自身としては、日本の先進性を活かし、官民の力を結集して、Global Human Development/Securityといったことを実現することですね。もちろん道は険しいですが、菅政権下において危機管理が安全保障に繋がり、国力が高まり、その力を基に各国と協調して政策を展開していくことを期待したいと思います。
菅総理には既得権益を壊す気概がある
――兼原さんは本誌(『Voice』2020年3月号)のインタビューで、安倍総理のリーダーシップを徳川家康型と指摘されました。官房長官時代の姿をご覧になったお二人から見て、菅総理の指導力をどう評価しますか。
兼原:先ほど述べたように、安倍前総理は外交・安全保障以外の政策は基本的に各閣僚に任せていました。優秀なチームを形成して役割を差配する様は、やはり家康のリーダーシップを彷彿とさせました。
一方で菅総理は、ご自身がいろいろなアイデアを積極的に出す方です。その意味では、備中高松城を落とすために軍師・黒田官兵衛とともに水攻めを考案して実行した豊臣秀吉に通ずる部分があるかもしれません。
高見澤:菅総理ご自身、総裁選の際に問われて、総理自らのタイプには言及せずに、秀吉を支えた実弟・豊臣秀長の名前を挙げられました。堺屋太一さんが書かれた『豊臣秀長 ある補佐役の生涯』(PHP文庫)が愛読書だと聞きました。兼原さんのように武将に喩えるのは私には難しいですが、あえていえば、前例を打破するという点では織田信長の要素もあるかもしれません。
官房長官時代の菅総理は、既存の制約を取っ払うことで目標が達成されるのであれば、実行を重視する方でした。たとえば役人が、この政策は500億円の予算では不可能だと言えば、なぜできないのか、いくらならできるのか、1,000億円なら目標を達成できるのかと問われ、時として、「じゃあ1,000億円を出そう」と即断するような方です。従来であれば、手段が限られているため、目標自体を引き下げたような案件も、菅総理は目標がはっきりしている場合なら「手段を考えて工夫しなさい」と言うのです。
兼原:私が官房長官時代の菅総理と一緒に仕事をして感じたのは、理由もなく残存する既得権益は思い切って叩き壊す気概をもっておられることです。また、かねてより省庁間の縦割りの弊害に強い問題意識をもっていて、横串を通して政府全体の力を出し切ることを、非常に重視されていました。役人が「それはうちの仕事ではありません」と拒もうものなら、「そんなことはわかっている。だったら、あの省庁と一緒に進めればいいじゃないか」と押し返す。役人が予算や時間の限界を指摘しても、本当にできないことなのか、やる気がないだけなのか、菅総理は瞬時に見破ってしまうのです。
高見澤:「できない理由を考えるより、できる方法を考えろ」とはよく用いられる言葉ですが、実践するのはなかなか難しい。その点、菅総理はまさに自ら実行されるタイプで、つねに前向きな議論を求めるリーダーです。我が国に山積する課題に正面から向き合っていかれると思います。
※無断転載禁止
掲載号Voiceのご紹介
<2020年12月号総力特集「米国の明暗、世界の大転換」>
- 田中 明彦/アメリカ民主主義の強靭性の行方
- 明石 康 /世界は国連の「歴史的経験」を活かせ
- 菅原 淳一/加速する三つの潮流、日本の通商戦略
- 三牧 聖子/「例外国家アメリカ」は終焉するか
- 小倉 紀蔵&岡本 隆司/「群島文明国家」が果たすべき使命
- 本村 凌二/歴史に学ぶ激変期の指導者の要諦
- 高見澤 將林&兼原 信克/安全保障とデジタルを連結せよ
<2020年12月号特別企画「菅政権、五つの課題」>
- 飯尾 潤 /【行政】調整型官僚から政策立案型官僚へ
- 小野 昌弘/【コロナ】欧州第二波を徹底検証する
- 高木 聡一郎/【デジタル】デジタル庁成功の鍵は「横断的主導力」にあり
- 山田 昌弘/【少子化】欧米モデルの少子化対策から脱却せよ
- 村山 斉 /【科学技術】「役に立たない学問」が国を救う
<ご購入はこちらから>
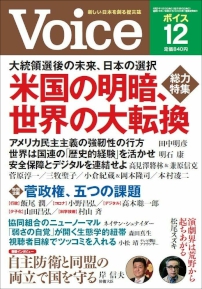
目次はこちら
View more


