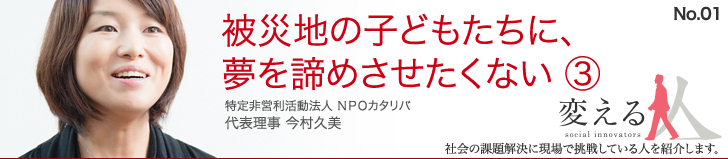私たちと地域の未来に、新しい可能性を

NPOカタリバ 代表理事 今村久美
今村久美さんのインタビュー第1回、第2回はこちら:
「家や学校を失った子どもたちに勉強の場を」
「子どもたちの未来に、たくさんの選択肢を」
NPOという生き方を開拓する
コラボ・スクールが根を下ろし、変わり始めた地域。女川町や大槌町の子どもたちを見て、今村さんは自身がNPOカタリバを立ち上げた頃を思い出すことがあるという。
「私の地元では、県内の国立大学に進学して、公務員や銀行の事務員になるのが親も親戚も安心できるので、いちばんの親孝行になるような感覚があります。それが私の場合、県外の大学に進学して、その上、大企業に就職すると思ったらNPOだなんて、もう意味がわからないって。親からも、『親戚や近所の人に聞かれると、なんて説明したらいいかわからない』と言われていましたね」
だが、震災がNPOに対する見方を変える。被災地で活動するNPOの姿がメディアによって伝えられ、今村さんも相次いで取り上げられるようになる。首を傾げていた人たちも次第に興味を示し、地元でもNPOを理解する人が増えていった。
「それまで一生懸命やってきた仕事を震災というひとつの機会が後押ししてくれて、認知度が高まって、社会的な立場が引き上げられたと感じています。ここで、評価に値する仕事をして仕事の価値を高めていかないと、ほんとうの理解は広がらない。上の世代の方々にNPOで働くという生き方の選択肢を理解してもらえるかどうかは、これからの私たち次第だと思っています」
2008年には「日経ウーマンオブザイヤー」を受賞した今村さん。ありがたく頂戴したものの、世代ゆえなのか、実感がわかないという。
「なんで女性だからって評価されなくてはいけないの、という思いが正直いってあります。たしかに昔は、女性が仕事をするということ自体があたり前ではなかった時代もあったと聞いています。現代でもNPOを立ち上げるということも珍しいし、さらに女性の代表者はそれほど多くないから、『NPOで女性だったら今村か』という消去法的な選ばれ方でメディア露出することも、きっと少なくない。でも、今の時代に女性起業家が特別視されることには、やっぱり違和感があります。大学を出て起業すること、NPOを立ち上げること、また女性が表舞台に立つことが、もっと普通にできる社会にしていけたら」
震災によって新たな事業に踏み込み、今まで以上に人の縁を強く感じるようになったという今村さんは、今年になって第一子を授かった。産休をとり、現地の仕事をスタッフに任せる中、一歩引いたところから法人運営全体を見渡すことで得られた新たな気づき。スタッフを信じて任せることの大切さ、そして仕事と私生活との距離感。NPOという新しい生き方を開拓する今村さん自身も、次のステージに向かって変わり始めているのかもしれない。

コラボ・スクール大槌臨学舎の校舎
コラボ・スクールがめざすかたち
今年の10月に新たな校舎へと移った大槌臨学舎もまた、次なるステップを踏み出している。あたたかみのある木造の建物には、教室や自習室とともに、ノートパソコンとヘッドホンを配備したスカイプルームが設けられている。
「フィリピンで英語の教育スキルを学んでいる現地の大学生に、週1回の英会話指導をしていただいています。支援をいただいている企業のテレビ会議システムとコラボ・スクールのスカイプルームを結んで、先方の社員さんに生徒に対してプレゼンテーション研修をしていただいたことも。大学のAO入試に挑戦する生徒には、その大学のOBとの間でスカイプを使って、面接の練習をしたりもしましたね」
廊下にはiPadとヘッドホンが置かれ、いつでもネイティブの発音を確認できるようにするなど工夫が凝らされている。こうした設備の充実した校舎に、110名ほどの中学生と40名ほどの高校生が通ってくる。習熟度別に分かれた授業のほか、自習室にもスタッフが待機していつでも質問を受け付けるなど、個々のサポートにも抜かりがない。さらに学校との連携強化も見据えている。
「女川では小学校との連携ができ始めていて、授業にコラボ・スクールのスタッフを参加させてもらっています。そういう関係性が深まれば、学校での学習内容を元にコラボ・スクールでの学習プログラムを組んで、勉強の効果をもっと高めることもできるはず。それって、ひとりひとりの生徒にとって、すごくいいことだと思うんです」

ところで、大槌臨学舎は大槌中学校の対岸にあり、すぐ近くに橋が架かっているにもかかわらず、子どもたちはスクールバスでやって来る。
「橋の幅が狭くて歩道がない上に、工事車両が頻繁に往来するので、通学路として認められていないんです。たった10数メートルの橋をわたれないために、川の向かいにある大槌臨学舎や仮設住宅には、少し遠くのバイパスまで大回りをしなければなりません。暗い夜道を歩かせるのも危ないので、バスを手配せざるを得ませんでした」(川井)
当初はぎくしゃくした教育委員会や学校とも、徐々に理解が得られ、良い関係がつくられてきた。地域や学校との連携がさらに深まり、子どもたちの学習環境が整えられ、そして復興が進んだときには、きっとこの橋も大手を振って渡れるようになることだろう。

城山公園から見える大槌町の様子(2013.10.23撮影)
「よそから来た人」だからできたこと
地域や行政との関係で苦労したのは、決してカタリバだけではない。震災後、多くの支援団体が被災地へと向かったが、現地で信頼を得ることができず、撤退していった団体も少なくない。
「やっぱり、時間をかけて続けていく中でしか築けない信頼関係があるんだと思います。私たちの場合は、3年経って、ようやくわかってもらえてきたのかな、と。女川では、町の教育関係の委員会にも、スタッフが参加させてもらえるようにもなりました」
子どもたちに放課後の学びの場とチャンスをつくってあげたいという、ひたむきな想い。上から目線で「べき論」を振りかざすのではなく、対話と創意工夫を重ね続けてきたことが実を結んだのに違いない。加えて、地域や子どもたちの様子を、ある意味で客観的にとらえられたことも強みだったのかもしれない。
「震災にあったのが故郷だったら、逆にスタッフも私も、ここまでできていなかったかもしれません。地縁血縁のつながりがあることで利害関係が深く、多くの人に気を使わなければいけない中では、やりにくいこともありますし。外から来た人間として、多少空気を読めないところがないと、突破できないこともいっぱいありますから」
震災直後は勢いで乗り越えたところもあったが、これからのロードマップをどのように描いていくのか。今村さんはコラボ・スクールの事業としての出口戦略に、いま想いをめぐらせている。
「日本全体を見渡せば、被災していなくても、女川や大槌と同じように厳しい状況に置かれている地域はたくさんあります。今、寄付や補助金を活用しながら被災地で取り組ませていただいている中でつくったプログラムやかかわり方を、全国の類似した課題を抱える別の場所で展開できるようにしていきたいんです。そうするためには、経営的にはコストを減らして、収入を複線化することも考えなくてはいけません。例えば、コストを半分にするとしたら、何ができるか、何をしなくてはいけないのか。コミュニティの力を借りることで、新しい何かが生まれては来ないか。いろんな角度から真剣に議論しています」
モデルのひとつとして注目しているのは、10年ほど前には学力調査の結果が大分県で下から2番目だった豊後高田市。これを危機ととらえた市は「学びの21世紀塾」を立ち上げる。退職した教員や英語の話せる経営者など、「子どもに勉強を教えられる人」による講習。学校も負けじと、放課後も自習できる学力アップコーナーをつくり、まさに市全体で学習サポートに取り組んだ。すると、2006年から8年連続で県内トップクラスを守るまで、学力が向上したという。
「これはものすごいコミュニティ・ソリューションだと思うんです。関与する大人の生きがいをつくり、余暇の時間をつかって市民みんなで教育力を上げて、その結果地域力を上げている。コラボ・スクールも、たとえばいまは遠方から雇用しているスタッフを、一部現地化するとか。そのためには、まずは現地の人たちを育成するモデルに変えていくことなど、今後のかたちを多数想定して考えています」
人口が減少し、少子化も進んでいく中で、地域全体の底上げに貢献できるモデルをどのように構築していくのか。その担い手を、どうやって地元で育んでいくのか。今村さんは、すでに一歩先を見据えているようだ。

あたたかみのある木造の大槌臨学舎
寄付者満足度を高めるという新たなチャレンジ
新たなビジネスモデルの構築を模索するカタリバ。震災前までは自治体や企業とパートナーシップを結んで事業型で運営してきたため、コラボ・スクールのように外部からの寄付金を得て運営にあたるのも、ほぼ初めての経験だ。
「私たちにとっては初めてのことばかりで必死にやっています。寄付をいただいて運営はできているけれど、その寄付が生かされていることを、どうやって実感していただけるか。それはもう悪戦苦闘しています」
寄付文化が根づいていないと言われ続けてきたわが国。それも震災を契機に、また寄付税制の拡充によって大きく変わりつつあるように思われる。
「震災によって、私たちだけではなく多くの団体に、驚くほどの寄付金が集まりました。これからは、そうした寄付をいただいて活動する側の責任として、寄付者満足度を高めていくことが大切だと思います。お礼や報告はもちろんですが、例えば寄付者の方々と協働するようなプログラムを通して、経験を共有しつつ成果を感じ取っていただくことが本当に重要だと痛感しています。寄付してくださる方々の心を動かし続けないといけませんから」
寄付実感を高めることによって築かれるウインウインの関係。ただ、そもそもの活動が、それに引っ張られすぎてもいけない。はじめて迫られる難しい舵取りも、先に取り上げたスカイプを通じたプレゼンテーション指導や英会話レッスン、ほかにも高校生による現地ガイドなどの実践によって、着実に寄付者の心をとらえているようだ。
「おかげさまで3年間支援を継続してくださる個人の方や企業さんもあって、その意味では寄付者満足度を保てたところがあると言えるかもしれません。でも、それに私たちが満足してはいけないので、まだまだ努力しなくては。海外のNGOやNPOを見ていると、寄付される努力をものすごくしていて、いい意味で競争している。被災地支援は、日本でもNPOが成長する良い機会になっていると思います」
寄付者満足度を高めるための取り組みを考えると、例えば1,000人から1万円ずつ集めるよりも、10人から100万円ずつ集めるほうが楽で、効率的だ。だが、その手間暇に生まれる価値がある。
「人が人を呼んでくる、熱意を運んでくる。やっぱりファンって、そうやって増えていくものだと思うんです。その人たちに対して努力をする姿勢に、私たちのあり方が問われる。お金の価値だけではなく、思いの価値に心を配る。寄付をいただいて事業を行うことで、すごくいろんなことを学ばせてもらっています」

事業運営に重きを置き、広報予算の潤沢ではないカタリバにとっては、日常生活の範囲で支援していただくことが力強いサポートとなる。
「こういう活動をしている団体があるということを、周りの人に少しでも広めてもらうということが、なによりもありがたいです。口コミやSNSを活用することで、カタリバやコラボ・スクールの広報の役割を担っていただけると助かります。あとはやっぱり、被災地のものを買うこと。地元の経済を回していかないといけないですから。もちろん、寄付もしていただけたらうれしいです」
最後に、いま改めて思うことを尋ねてみた。
「私たちくらいの世代って、生まれてから欲しいものは満たされている飽食感があるから、NPOとか社会貢献に興味が集まっているのかなと感じていました。ところが、被災地の子どもたちは、まったく違う立ち位置から社会をみつめ、地域のためになることを考えている。いま置かれている環境をパワーに変えられる気がします。その子どもたちの力になれるように、これからも頑張っていきます」
【今村久美 略歴】 いまむら くみ*1979年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。大学在学中に2001年に任意団体NPOカタリバを設立し、高校生のためのキャリア学習プログラム「カタリ場」を開始。2006年には法人格を取得し、全国約400の高校、約90,000人の高校生に「カタリ場」を提供してきた。2011年度は東日本大震災を受け、被災地域の放課後学校「コラボ・スクール」を発案。
【取材・構成:熊谷 哲(PHP総研)】
【写真:shu tokonami】